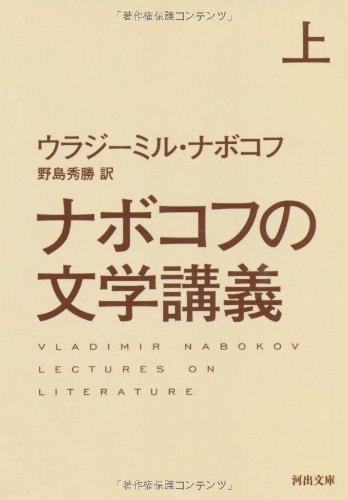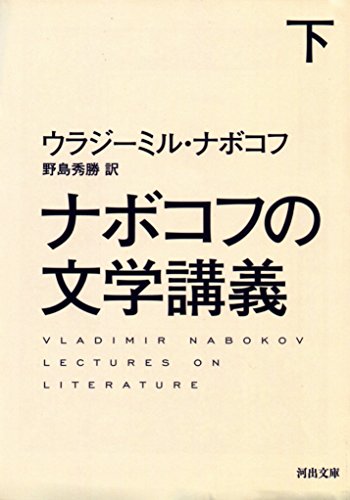どっきりどっきりDON DON!!
(ネタバレみたいな要素もあるので、『旅する練習』を読む前に読まない方がよいかもしれません)
『おジャ魔女カーニバル!!』もまた、よく聞いていた曲である。というよりも、足を運ぶ先々で、登場人物の少女の姿が浮かぶとき、ほとんどはこの曲を想起し、実際に慌てて聴きもした。すぐ始まるので公式で聴いて欲しい(埋め込みはダメみたいなのでとんでください)。
「これがこの旅のテーマ曲なの」というわかりすぎる台詞はさすがに省いたが、作中で一番多い書き直しを要しつつ、明らかに少女の生き様を表すものとして自ら説明させることになったのは、その歌が、明るさが、旅の背景にいつも流れていてほしいと思ったからだ。ちょうど、アニメ『おジャ魔女どれみ』の時系列的には最後のシリーズの最終回を見ればわかるように。
また、それによって、この曲名にある「カーニバル」という言葉が、それ以後、また再読の際に意味をもって響くための、解釈の糸口になってほしいと図々しくも考えていた。
カーニバルとは、底の抜けた明るさの中で、多くの人が入り交じり、遠慮無いお喋りや道化によって聖俗や貴賤も反転するか区別がなくなる場である。それを文学理論に用いたのがミハイル・バフチンで、ちょっと目立ちすぎるかもと思ったが、今回の小説はそのカーニバル論を借りて、ポリフォニーに弾ける前にあえてそこに留まろうとする実践でもあった。すでに言及している評者の一人か二人はいるかも知れないし、逆に反論しているみたいな形になっているかも知れないけれど、まあいいだろう。
鳥をはじめとする動物や(山)川草木、そこに暮らした人々、文学者、民俗学者、サッカー選手、チームスタッフ、少女アニメ、剣豪、仏神、書き手や登場人物、生者もいれば死者もいる。また、公的機関の文書も含めた雑多な文章。この世界に残された声を全部全部にぎやかに集わせながら、それでも静かなカーニバルとしてテクストの道はある。本当は、佐原にて伊能忠敬と小林一茶、神栖にて高橋虫麻呂、前述した3人のサッカー選手たちも何も、とにかく詰め込みたかったが、進路と進行上の理由で沢山あきらめた。まあ、これだけにぎわっていれば目的は果たしているはずだ。
そうして出てくる全てにかなり明るいお喋りや主張をはっきりさせて気に障る人もいるかも知れないが、なぜそんなことを今回はできるかといえば、それがカーニバルの場として機能することを「語り手」が願っているからだ。そこでは、あらゆるものが反転する可能性を残している。各文化の聖俗じみた上下も、希望と失望も、練習と成果も、生と死も、読むことと書くことも、事実と虚構も。
『おジャ魔女カーニバル!!』の説明に感銘を受けた「語り手」にとって何より痛み入りながらも意義深いのは、この世界のひと時をそのように美しく楽しい歓びにあふれた、しかも一人の少女のためにそうであるようなカーニバルとして書き表すことだ。
そもそも誰であれ、人間がこの世で生きるというのは、そんな風にあるべきではないか。
しかし、カーニバルには終わりがくる。もともと、イエスにならって己を律する四旬節のために謝肉祭はある。信心の至らぬ者たちが辛い断食の日々を前に大騒ぎをしたのが慣習になったというが、その時間を「語り手」が都合よく引き延ばし、辛い実感に目を背け続けてこの小説を終わらせるのは、最も重要な戒律である「練習」の意義にも反するだろう。辛いことを辛いことと思わぬ素振りをできるのが忍耐や練習の正体であるはずがない。そんなぬるいところで安穏としているだけの「語り手」に、少なくとも自分は興味がない。生きている限り生起するあらゆる齟齬を正そうとし続けるところに、練習の永遠性があるのだから――だから、描写もまた完成しない。練習を続ければ続けるほど、風景が、動植物がその本当に近づけば近づくほど、説明との境をなくし、小説には収まらなくなるだろう。しかし、小説として収まりの良い描写は、より鮮やかに見えたところで、その時あるものを留めて後に再現するには全く役に立たない。カーニバルの歓びを今に想起したいのではない、カーニバルが行われていたその時に、嘘偽りなく居合わせたいのだから、「表現」なんぞに用はない。
シーモアが書き残した「ものを書くということがおまえの宗教である以上」という言葉をぐるぐる巡っている限り、光は不可能性の中の継続のうちに起きる目眩のようにしか見ることができない。それでいて最も大きな希望、強い光は、矛盾するようだがカーニバルの先にある。そこでは胸を張ったカワウが羽を広げているはずだ。
だから、「書き手」が存在するための必然の中に結末を見たことは、悲しみながら嬉しくもあった。そのこもごもは、途中まで少女の名前も知らなかったはずの一度目の読者に味わえるものではないだろう。文章が残ればカーニバルは二度三度、何度でも催されよう。そこでなら、結末の意味もまた反転するようにと願う。もちろん、それは「結末」と呼ばれるものがあるという妙な前提そのものに対してもそうだ。
まあそんなことは、もちろん読み手次第でしかない。そこには前も書いたように十人十色の意義があるし、みんながみんな、もしかしたら同業者の顔をした小説家でさえ、書くことについての切実に考えているわけではないのだ。いや、切実なのだが、そこにはさほどの練習が伴わないのである。それでも、だから自分はこの小説を、ナボコフにだけは、その講義にもぐってこっそり提出してみたかったなんてことを思ったりする。
こういう全部を少女アニメの主題歌の中の一語「カーニバル」に託しているわけではないものの、小説を、テクストを、言葉を読むとはそういうものだと自分は学んできたし、考えてきたし、その練習を続けてもいるつもりだ。
森羅万象のなるべく多くをと微力ながら渉猟してきて、自分の向かうべきものに、あらゆる意味でぴったりはまるものが、この素晴らしい世界にはちゃんと用意されているということは何度も実感したことである。
今回、「おジャ魔女カーニバル!!」という多くの意味を明るさにくるんだ素晴らしい歌の、この歌詞、曲調、タイトル、もっと言えば自分の若い頃に放映されていたのでなければ、こんなことはできなかったのだから、本当に感謝している。そんなことを言い始めたら、コロナウイルスだってそうなってしまうのだけれど。
これまでも、こういう全体の解釈を導く腹づもりの言葉を節操なくばらまいてきたつもりではあるけれど、それがどんなに踏まれながら素通りされようと、「語り手」ではない自分から言うことは何一つないと思っているし、実際、訊かれない限りは言ったこともない。
連投の冒頭で書いた通り、今回に限ってなぜこんなことをわざわざ縷々、その中のごく一部であるとはいえ述べているのかと言えば、これも少し書いたけれど、何より、この小説の「語り手」が、限りなく自分に近い存在だからだ。
だからこそ、「語り手」の小説家の文章が本になったと「想定」されることは望外の喜びだった。まさに望んだ外から、表紙に印字されている自分と「語り手」を、これ以上ない形で重ねてもらえ、「書き手」となることができたのだから。
おかげで、後からこんな文章に書き込まれた意味でさえ、今回ばかりは、小説に足すことが許されていると甘く考えている。さらには、こんな説明さえあのカーニバルの道中にこびりついて欲しいということを。
そして、その思いはさらに外へと足を延ばす。
何度も辿ったあの道で人間の営みは続くだろうが、もしこの小説があることでそこを歩こうという読み手がいれば、それがブログやSNSに書かれても、誰にも見せない日記に書かれても、また書かれなくても、カーニバルはもっとにぎやかになるだろう。すでに自分は、「書き手」の担当編集者がその旅程を辿ったことを知っているし、「書き手」が出した小説の装幀家が同じことをやろうと企てているのも知っている。書店員が得難い意欲をもって売り場に並べてくれているのも、アントラーズを愛する人々が、書かれた土地の人々が、手に取ってくれているのも知っている。
それら現実が「書き手」にどんな救いをもたらすかをこれから思い知ることになるなら、「小説に、文学に何ができるか」という大抵は自己弁護や時間稼ぎのために虚ろに使われている質問に、響く刺さる癒される以上の意味を、私の好きなこの世界のところどころにもたらせるのではないかと楽天的なことを考えている。
「おジャ魔女カーニバル!!」だけを聞くなら、一番入手しやすく音質もよいもの。