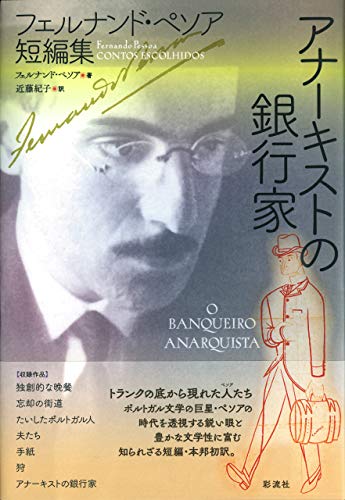『案内係 ほか』フェリスベルト・エルナンデス/浜田和範 訳
最近、あんまり小説を読まないが、これは何度も読み返したし、たくさん書き写した。ピアニストから転身したウルグアイの作家の短編集である。
いきなり個人的な見解を言えば、演奏すること、書くことといった行為の内実にとことん興味があり、全てがそのことに関わるように書いている作家だと思う。その思弁が、それぞれの物語というかそれぞれの「状況」の中にちょくちょく差し挟まれ、だからそんなことを考える由もない人にとってその記述は幻想的や「シュール」といった印象になるだろう。そして、その通りにシュルレアリスムと言って構わない面もある。シュペルヴィエルも讃えているくらいだ。
アンドレ・ブルトンはシュルレアリスムを「口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスム。理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」と定義しているが、そこに範をとっているかのような記述は、そこかしこに発見できる。
私は誰に対しても、特に自身に対して用心したい。まるで十本の指が私をくすぐろうと脅かし、それを避けねばならないかのように。もう一つ用心しなければならないのは、分類するという悪癖だ。秩序というのは手段としてはいいが目的としてはよくないのは確かだが、誰もがそれを忘れ去り、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまうのだ。
(p.269)
フェルナンド・ペソアがもっと小説を書いて、断片に灯る光と光の間に横たわる薄暗さに目をつぶることができたならこんなものになったのかも知れないと思わせるが、そんな推測も、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまった結果にしかならない。誰もが、こんな風に文字が連なることで何かを言った気になっているのだろう。
とはいえ、この前段も含め、こういう自己否定を繰り返している人間の書き物が似てくることは否定できない。彼らが隙あらば行う自己言及は「自分の行為を、その行為の副産物によって否定する行為」で、やればやるほどに狭まっていかざるを得ず、新たな否定の隙もないと思えるほどの狭さ自体によって似てくるからだ。それは書くという行為のどん詰まりである。どん詰まりだが、アキレスと亀の距離のように、永遠に続く有限の中の無限とも言える。
だからこそ、彼らが文を書く上で重視するのは実感である。自己否定に塗れた行為の救いは、自分を否定する能動つまり今まさに書いている時にだけ存在する。書くことが、究極にはそんな行為であることを思い知った人間は当然、何を書いていようと、次の箇所で否定されているようなことに意義を見出すことはできない。
私は意を決し、彼には理解できないことを説明してやった。曰く、私はどこかへ行くかなどまったく興味なしに書いているのであり――たとえそのこと自体がどこかに行くことになるとしても――さしずめ次の目的地は、悦びを引き出し必要を満たすこと以外にない。私の中にあるこの必要というのも別に、何かを教えることになどまったく関心はない。もし私の書くものが結果として、楽しませ感情を揺さぶるものに関心を示しているのであれば、それも結構。だが私は少しずつ埋まってゆくこの素晴らしいノートを埋め、やがて埋まった日にはフルスピードで読んでみるという以外、何もしようとは思っていない。
(p.277)
他人の楽しみや学び、それに伴う賞賛は「結構」だが、「関心はない」のだ。作中人物はノートを埋めて読むだけと言うが、出版社の、精一杯わかりやすい紹介に努めたであろう文を読んでもらえば、書くことについての考えを頭から離さずどう小説にするかについて、相当な関心を持ってあの手この手で「状況」作りに取り組んでいたことがおわかりいただけるかも知れない。
思いがけず暗闇で目が光る能力を手にした語り手が、密かな愉しみに興じる表題作「案内係」をはじめ、「嘘泣き」することで驚異的な売上を叩き出す営業マンを描く「ワニ」、水を張った豪邸でひとり孤独に水と会話する夫人を幻想的な筆致で描く“忘れがたい短篇”(コルタサル)「水に沈む家」、シュペルヴィエルに絶賛された自伝的作品「クレメンテ・コリングのころ」など、幻想とユーモアを交えたシニカルな文体で物語を紡ぐウルグアイの奇才フェリスベルト・エルナンデスの傑作短篇集。
僭越ながら、ここまで書いたことには、自分自身かなりシンパシーを感じる。また一人そのような人物が過去にいたという証拠を集めて、これが出版された2019年の年末はとてもいい気になっていた。
特に次の記述は、そこまで読んできてこの興味深いフェリスベルト・エルナンデスが何をしているか見てやろうと息巻いていた上に、2018年頃の自分が小説という形で実現しようと取り組んでいたことが書かれていたものだから、かなり驚いた。これが客観的偶然と呼ばれるものなら、自分のやってきたことも順調かつ敢えなく狭まってきているのだと思えてまんざらでもない。
親愛なる同業者、そう、そう、今読んでいる君のことだ。ここに並ぶ文字の目、穴、本体のすき間から、尖った角の後ろから見ているんだからな。君も同じことをやろうと試み、二人して文字のあいだを移動する際に武器を隠したりすれば、傍目からは無邪気に隠れんぼでもしているような格好になる。つまずいたらご用心!
(p.263)