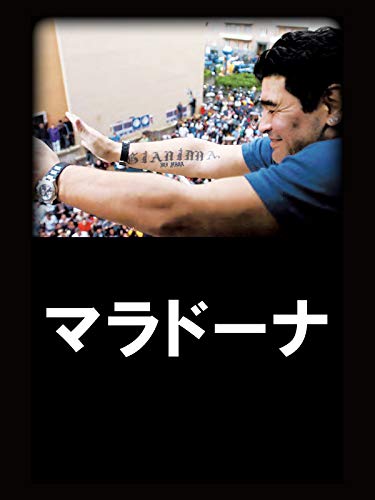本書は一時期、久保建英が移動中に読んでいる本として話題になった。本来、みすず書房の本を読むフットボーラーなど存在してはならないからだ。読書家で知られた元レアル・マドリーのエステバン・グラネロは「チームメイトと文学について話すことはあるか」と問われ、苦笑混じりに「あまりないね…」と答えている。彼が遠征にカフカの本を持っていくと周囲は震撼したという、基本的にはそんな世界だ。
五年前に亡くなったガレアーノは、ウルグアイのジャーナリストだが、クーデターによる投獄、亡命、死の部隊のリストに入れられてさらにスペインへ亡命し、ウルグアイの民政移管が完了するとモンテビデオに戻ってきて発言を続けた。
自分も全てを読んだわけではないがその作品はジャンル分けが難しく、本書もサッカーエッセイの要素が最も強いとはいえ、その語彙はとにかく広範囲に渡り、戦争から経済まで様々な歴史が、個人史が、サッカーと結びつけられている。
日蓮宗から派生した創価学会信者であるロベルト・バッジョは仏教から我慢の心を与えられた者として、エウゼビオは貧民街からサッカー界にたどり着いた者として紙幅の半分を割かれるのは、もちろん、依頼主からの外的な制約もあるだろうが、あらゆる歴史が集い、また生まれる場としてサッカーがあるという著者のスタンスを示しているように思える。
そんな中で、マラドーナに関するエッセイは、群を抜く全体の長さだけでなく、記述内容もまたいささか例外的に映る。
口を開くとどうにも止まらなくなるマラドーナだったが、ひとたびボールを蹴り出すとなおさらとめどない。一度限りの驚異を次々と発明し、コンピュータを混乱させて喜ぶ彼の神技を予見できる者はひとりもない。彼はスピードにものを言わせるプレーヤーではない。短足の鈍牛というところだが、彼がボールを運ぶとき、ボールはまるで足に縫いつけられたかのようであり、身体じゅうに無数の目を持つ。彼はその曲芸でフィールドに火を放つ。たとえ何千本という敵の脚に囲まれ尽くそうが、彼ならゴールに背を向けたまま電撃シュートを放ったり、離れたところへ考えられないようなパスを送って試合を決めることができる。仕上げに、ドリブルをしながら敵を蹴散らしてゆく彼は、誰にも止められない。
(p.263)
プレーを評するためのこうした表現がいつどのように生まれ、育まれ、人口に膾炙していったのかという歴史について明るくはないが、ガレアーノがやや荒唐無稽にも思えるこういった比喩表現をこれほど並べ立てるのはマラドーナの他にはせいぜいペレぐらいであることを考えると、サッカーを語るための表現について、言葉と現実の乖離に敏感な人々は、ある程度は自重していたと知ることができる。
そこで使われた特別な言葉が、鈍感な人々によって、それ以外のプレーヤーにも自重なく使われることで、こうした語彙が世間に広がっていったと思われる。メジャーリーグ一年目のイチローのただ一度の送球に対して実況リック・リズが当意即妙に与えた「レーザービーム」という言葉が、後にその種の見事な送球全てに用いられたように。
もちろん自分はマラドーナの全盛期を目の当たりにしてはいない。それでも、こんな映像の、例えば 2:47~、ボールを跨いだ足をゆったり音もなく戻した瞬間、足首のスナップだけでボールを正確に弾くと同時に身体もそちらへ跳ばす――顔は絶えず前を向いている――のを見てなんだか泣きそうになるのは、それが「一度限りの驚異を次々と発明し」ている姿に映るからなのだろう。
マルセイユ・ルーレットとして知られる技を試合の中で使いこなした最初の人物はマラドーナだという話もある(実際、それはマラドーナ・ターンとも呼ばれる)。同じように、死してなお残されている数々の動画には、発展を遂げた現代サッカーで名手達が見せている妙技の数々の初期形であり完成形が、いくらでも見られる。やはりその中のいくつかは「発明」に違いなかっただろう。
練習中のリフティング一つとっても、難度を上げていくことが目的化された今日のフリースタイルとは、まったく異なる驚異がそこにはある。フリースタイルでは、身体からボールを離さず運動エネルギーをなるべく小さくしたボールに微調整を加えながら複雑な技を繰り出す。そうしたテクニックはもちろんマラドーナも見せる。しかし、それ以上に惚れ惚れするのは、肩でのリフティングを小さなモーションで数メートル上まで弾ませ続ける力強さや正確性とか、それをしながら次の瞬間にはいつでも爆発的なドリブルに移行しそうな姿勢や体の動きで、つまりマラドーナがやっているのはリフティングではなくサッカーだった。
リネカーは、ワールドカップでマラドーナの練習を見て受けた衝撃をこう振り返っている。「ボールを思い切り真上に蹴り、落ちてきたらまた蹴る。それを13度も続けたんだ。最大3歩しか動かなかった。僕たちは『不可能だ』と言って見ていた」
リネカーが見たのは下の動画の 1:22~ のようなものだろうが、当時世界有数のストライカーが相手選手の様子に目を奪われ、ボールの高く打ち上がる回数をわざわざ数えているというのは、単純にワクワクする。それは「思い切り真上に蹴」ることを繰り返すことのできるマラドーナにしか作れない光景だ。
もちろん、プレー動画では、メッシとの比較のたびにしつこく言及されるように、それがいかに間延びした中盤の緩いプレスの中で行われていたかも見ることができる。
しかし、ディフェンスラインを高くしコンパクトに保った中盤守備で相手を狭いスペースに閉じ込めて自由にさせず高い位置からのショートカウンターを狙うという現代サッカーの基本戦術もまた、ナポリ時代のマラドーナを止めるため、ACミラン時代のアリゴ・サッキが修正を加えつつ考案した戦術だった。
つまり、マラドーナは相手の「発明」にも一役買ったのであり、戦術家であるジョゼップ・
とはいえ、また別の動画を見れば、かつてのサッカーではそんなゆるい中盤から一転して、寄せてきた守備者がいかに荒っぽい肉弾戦を仕掛けていたかも確認することができる。そのナポリ時代を、同リーグでプレーする選手として見ていた現名古屋グランパス監督のフィッカデンティは、「今のルールならば退場相当の徹底マーク」だったと述懐している。「命以外は何を奪われても仕方ないくらい厳しく止められる中で、あの活躍だった。唯一無二の存在だった」
それと闘い続けながら当時世界最高峰のセリエAを下位チームの救世主として入団して二度の制覇に導き、86年メキシコワールドカップを「マラドーナのための大会」と呼ばせるほどの活躍で優勝の栄冠に輝いた。自身を最も有名にしたプレーである五人抜きについて、直前に「神の手」によってゴールを陥れた自分にさえフェアな守備を貫いたイングランドを讃えているぐらいだ。
それにしても、サッカー史上で最も物議を醸すゴールと、最も素晴らしいとされるゴール、その二つが、わずか五分の間に一人の選手によって生まれたという事実の凄まじさよ。
時代が進み、サッカーは変わり、言葉も変わった。スポーツ新聞の一面ならまだしも、サッカー批評に荒唐無稽な言葉はほとんど見つけられないし、自浄作用さえ働いているように見受けられる。サッカーにまつわる言説は、一抹のさびしさもないわけではないが、誠実に、成熟したと言えるだろう。
いずれにせよ、そんなサッカーにまつわる全ての歴史の中に欠かせない選手であったことは疑いようがない。だから、その歴史は、ガレアーノがたびたびそうするように、思わぬところへ迂回してなお繋がってくる。
『キャプテン翼』の作者、高橋陽一は、マラドーナの死について「有名な5人抜きをはじめ、漫画のようなプレーは翼だけでなく作品全体に影響を与えてくれた」と語っている。
その作品世界では、荒唐無稽なシュートやドリブル、ディフェンスが繰り広げられるが、それはまさに「電撃シュート」のような比喩表現の紙面における具現化であった。
しかし、そのためにはまず比喩表現がなければならず、さらに前には比喩表現に値するプレーがなければいけなかった。そのインスピレーションを最も多くもたらしたのがマラドーナであったことは間違いがない。そして、ピッチ外での言動やコカイン、エアガンも含め、プレーと関係なくサッカー選手の有り様を表現する語彙にも、多大な貢献をしただろう。
それはともかく、その華麗なプレーから芽吹いた荒唐無稽な表現に満ちたサッカーアニメを食い入るように見た世界中の少年たちの中に、その後のスタジアムを沸かせた多くの名選手たちが、そしてリオネル・メッシもいたのだった。
マラドーナが最もサッカーを愛した選手だとは口が裂けても言えないが、最もサッカーに愛された選手は誰かと訊かれた多くの人はその名を口にするはずだ。
様々な意味で成熟した言説の支配する今日だったら、同じような存在になれたかどうかはわからないとはいえ、その時代に残された記録を色々顧みてみると、世論が「最もサッカーに愛されている」という彼の特権に抗い紛糾してきた歴史というのがうかがえる。もちろん、それは同時に、最後には「神の子」という破格の存在に屈してきた歴史でもある。
2018年になってもなお、ロシアワールドカップで母国アルゼンチンの試合観戦に現れれば、人々は試合の次に、その一挙手一投足を注視した。
ナイジェリア相手の試合最終盤、アルゼンチンのロホが、決勝トーナメント進出を決定づける劇的ゴールを決める。興奮さめやらぬ人々がふとVIP席を見上げると、スタジアム中でなぜかその一点にだけ差した輝かしい光の中で、天を仰ぎ、両手を広げているマラドーナの姿があった。
こういう神話的な場面が彼には数多く訪れ、そのたびに堂々と振る舞った。しかし、そんなにわかには信じがたい出来事の数々さえ、彼がピッチ内で描いた神話には到底及ばないせいで、また人々はそのプレーを思い起こし、彼に屈することになるのだ。歴史はこうして繰り返されてきたし、これからも続く。だから、ロベルト・バッジョはこんな言葉でマラドーナを送り出している。
「わたしたちが何世紀もルーブル美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザを称賛できているように、これからの世代はディエゴがそのサッカーで描けたことを称賛していくだろう。それはこれから何世紀にもわたって残る。これがひとりの人間の偉大さを決めるのだ。まだ1990年ワールドカップ準決勝や、数々のピッチでの対戦を覚えている。ディエゴ、良い旅を。永遠なる穏やかな光の旅に、ボールを持っていくことを忘れないでくれ」
『ANSA通信』より
「ディエゴはモナ・リザと同じ」「彼こそが背番号10の神」バッジョやデル・ピエロもマラドーナの死を悼む(SOCCER DIGEST Web) - Yahoo!ニュース