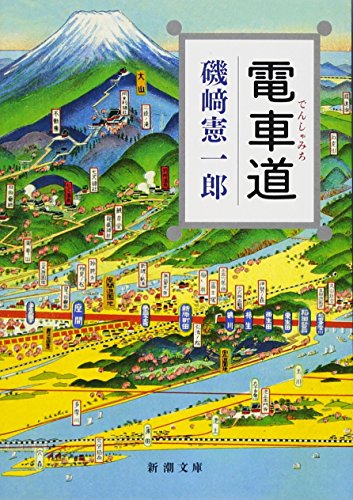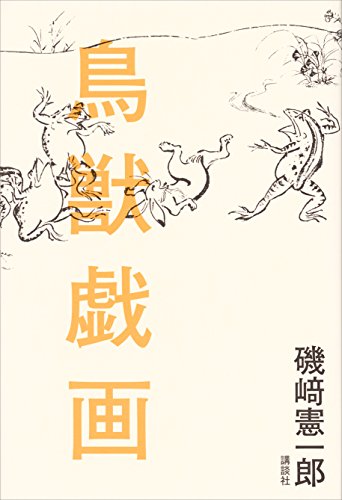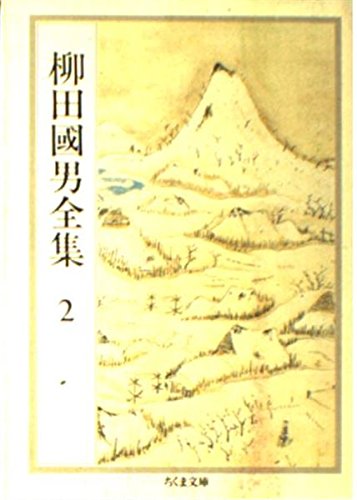文學界2020年8月号で、磯﨑憲一郎さんと対談した。
コロナ禍、緊急事態宣言が解かれて少ししてお目にかかるという状況だったが、家から出ない間は、対談準備の本が読めて楽しかったのを覚えている。持っているものもいくつかあった参考文献はほとんど読んだ。
それで感じたのは、『日本蒙昧前史』は史実を元にしてというか、現実を元に書かれた本を読んだ語り手が、読んでいる時の自己中心的で脱線多く思いつきに翻弄される状態のまま、歴史をいいように語っていくような小説だということで、そういう「読んでいる時の気分そのもの」みたく書かれた小説は珍しい。
その中で一番面白く読んだのが本書だった。特に、新聞記者である夫に入院中の妻が宛てた手紙は素晴らしくて、横井庄一の奥さんの自作詩が申し訳ないがちょっとこれは読んでいられないぞと思った後だったので、感動した。
▼一月八日「今時分、三木総理のそばをぴったんこのことと思います。暖かいところから寒いところへ帰ってブルブルなのでは? 風邪に御用心!! 紀は住生活の面ではとっても優雅にやってます。昨日、午後三時頃入院。さっさと片付けてベッドに横たわったのは三時四〇分。母が帰り、四時半には夕食。食後お風呂。その最中に父がやってきて六時四五分までいて七時のニュースが終った頃、お医者様が現われ三〇分位病歴その他のことを聞かれました。
お食事が病院食でちょっぴり口に合わないのが残念ですが、お腹のガキさん達を大きくするためにせっせと食べせっせと眠ってますから安心して下さい。昨夜廊下で中学の時の同級生のドクター中村にばったり。「入院したのよ」といわくいんねんを説明すると「八〇ミリだったら(頭の大きさが)育つと思いますよ」を聞きひとまずホッ。でもね、入院してよかったと思うの。以前はそんなこと全然なかったのにきのうあたりから歯を磨きながら立つとか病室を歩くのがとっても大儀になってきたんです。足がバーンとはってしまってお腹がズシーンと重くって。だからベッドの上にデーンと横たわってます。きょうから胎盤機能検査とかいろいろはじまりました。冗長な手紙で軽蔑されそうだけどベッドで横になりつつなのでお許しあれ。風邪と過労に御用心。 紀」
『日本蒙昧前史』にこうしたチャーミングな手紙は引用の形ではなく、作者のよくいう「語り口」の中へ、落ち着いた記述として取り込まれている。方法論の違いというよりは、読む書くという行為に対する捉え方の違いのような気がして、そういう疑問に基づく細かい質問を沢山してしまった。
困ったら見ようと思って、読みながらためていた打ち込みのメモを持参したが、それほど見返すこともなく、考えていたけれどしなかった質問も多い。メモはほとんどが引用だし、殴り打ちに近いので今見ると自分でもどういう意図だったかわからなくなっているものもあるが、引用した断片だけ読んでもこの小説は十分面白いので載せておく。
以下、その対談用メモである。
p.142
世間の目など気にしながら生きることじたいが、健康な肉体に対する冒涜であるのみならず、先取りされた深い後悔でもあるのだと信じて疑うことがなかった。
p.150
もともと人付き合いなど良い方ではないが、しかし改めて考えてみれば、他人と仲良くせねばならぬという、少なくともそう見せかけなければならぬという義務から、老いることによって解放されたのだとすれば、これこそが長い間待ち望んでいた慰労、大いなる達成であるはずだった。
p.213
作品の構成上ほとんど必要ないと思われる下着姿のサービスシーンでも、胸元まで露出させるベッドシーンでも、今ではさしたる抵抗も感じることなく受けてしまっていたのだった。するととつぜん、憤りと入れ替わるようにして、彼女は猛烈な羞恥心に襲われた。
p.249
ただ同じ会社に入ったというだけで、同期入行だというだけで、新人たちはまるでお互いが十年振りに再会した幼なじみでもあるかのように、親密に握手をしたり、肩を叩きあったり、ときには抱き合ったりまでしていた、それがこの場では当たり前なのだった。こいつらはみんな正気なのか? どこの誰だかよく知りもしない相手と抱き合ったりして、本物の幼なじみに後ろめたさを感じないのか?
登場する出来事の年表
・1970 大阪万博
・1970/11/25 三島由紀夫、割腹自殺
・1970~1987 福角戦争
・1972/2 横井庄一帰国
・1972/4/16 川端康成自殺
・1976 ロッキード事件
・1976/1/31 山下家の五つ子誕生
・1984~1985 グリコ・森永事件
・1984/3/24 三菱銀行人質立てこもり事件
・1985/6/18 豊田商事会長刺殺事件
・1985/8/12 日航ジャンボ機墜落事故
・1986(発覚) 平和相互銀行事件
池田勉は元警察官僚、伊坂重昭は元検察だが、前者が農林省、後者が警察官僚になっている。
・1997 横井庄一死去
『日本蒙昧前史』登場順
・1984~1985 グリコ・森永事件
・1984/3/24 三菱銀行人質立てこもり事件
・1985/6/18 豊田商事会長刺殺事件
・1985/8/12 日航ジャンボ機墜落事故
・1986(発覚) 平和相互銀行事件
↓
・1970~1987 福角戦争
↓
・1976 ロッキード事件
・1976/1/31 山下家の五つ子誕生
↓
・1965~ 万博開催準備 千里への道 用地買収
・1970 大阪万博(千葉の少年) 目玉男
・1970/11/25 三島由紀夫、割腹自殺
↓
・1972/2 横井庄一帰国
・1915 横井庄一誕生
・1997 横井庄一死去
p.28
政治家は来年還暦だったが、恐らくまだ二十歳を過ぎたばかりだろうこの女は、なぜだか自分よりも年上のように感じられた。
鳥獣戯画p.45
身長百七十センチの彼女を前にしておかしな話ではあるのだが、じっさい医者からすると彼女と五歳の娘の姿が重なって見えてならなかったのだ
p.34
おかしな話だが彼女はときおり、自分よりも四十歳近く年長のこの異性を、今も水上で実家の温泉宿を手伝っている、二歳年下の弟のように錯覚することさえあったのだ。
p39
ただでさえ低い政治家の背丈が、もう一段低くなっていた、気のせいかとも思ったが間違いない、もともと政治家は彼女よりも頭一つ小さかったのだが、今、目の前で、ふらふらと力なく、ほとんどパートナーに凭れ掛かるようにして踊っている老人の頭は、彼女の肩の下にあった、政治家の身長は縮んでいた。
「齢六十七にして、私は未だ、私の人生に囚われたままだ……」
p50
そのまま四週間の入院生活を送った、帰宅した彼女の両頬は、見違えるような艶と赤みを帯びていた、体重も増え、これは気のせいだとは思うが身長も少し伸びたように見えた。
p121
「容姿はともかく、この男は途轍もなく大きかった! 背丈はエレベーターの天井に頭をぶつけるのではないかと心配になるほど高く、腰回りも日本の大人二人分はあろうという太さだった、この男こそ大男、巨人と呼ぶに相応しい!」
p142
この樹上にあっては、進化の時間が進めば進むほど、生物は小型化してしまう。
p148
「魔人が現れたのだ……」小鳥にとってみれば自分はそれほどまでに巨大で、圧倒的な力を持つ強者なのだ、ならば自分はこの、素手で触れればすぐに砕けてしまいそうな、見るからにか弱い生き物に向けて、どんな施しをしてやれるのか
p151
生身の人間が鉄の塊にぶつかっていっても、勝ち目はない
p.29
物知り顔で、麻のワンピースや半スボンや刺繍入りのセーターを売っていることに後ろめたさを覚えた。
p.36
「これはつまり、後ろめたさだな……」三年に亘って大蔵大臣の座に居座り続けた前任者によって、職員の大半は懐柔されていた。
p72
いくら生活のため、家族のためとはいえ、盗み撮りまでして金を稼いで、自分が恥ずかしくないのか……父親は記者という仕事に就いて恐らく初めて、心の底から同業者を軽蔑した。
p82
初めて保育器の中の子供たちと対面したあの晩、痩せ細った小さな末っ子を見た自分は絶望し、まるで親鳥の帰りを待つ巣の中の雛のように弱弱しいこの子が、いずれ自分の足で立って歩み、人の言葉を話し始めるなどとてもではないが想像できなかった、人生の時間を捨て去ろうとしていた、父親はそのときのことを思い出し、自らの未熟さを深く恥じたのだった。
p74
「恥ずべき行為とは分かっていながら、父親はその記者を足蹴にしてしまった、傍目からは妻を守ろうとする夫の正当な防衛行為のように見えていたかもしれない、しかし寄りすがるその男を振り払おうと右の踵を思い切り突き出したとき、父親は明確な憎悪の念に駆られていた、頭に血が上って顔が紫色に染まっていた、そのことでそれからしばらくの間は、彼は自己嫌悪に苦しめられた」
p30
映画俳優というのは大人も子供も皆清潔で、澱みなく話し、始終快活に動き回っていて、貧しさのかけらも感じさせないものだとむしろ感心した。
p.32
この時代には、職を失うことに人生の終わりめいた絶望感が伴うことがなかった、それは戦中戦後の最悪の時代を生き抜いた記憶が、人々の肉体の奥深くに残っていたからかもしれない、別に命まで召し上げられるわけではないし、真夜中に空から焼夷弾が降ってくるわけでもない、今晩食べる物がないわけでもない、それに比べたら失職なんて、人生の時間を費やして悩むべき本当の問題じゃあない、耐性と楽観性が、若い彼女を守ってくれていた。
電車道p.134
兵役だってしょせんは形を変えた労働じゃあないか? せっかく一人で飛行機を操縦しているのだから、船上から逃げて燃料の続く限りどこまでも飛んで、山の中にでも無人島にでも不時着すれば半分以上の確率で生き延びることができるのに。瓦屋根と板塀で囲った家なんかなくとも人間は生きていける、川で魚を釣って山菜を取って、洞窟に住めばよい、一人孤独に生きることは恐れるには足りない。それなのに私たちは、義理や愛情や友情の網にがんじがらめに縛られてしまって、身動きが取れないのだ。これがお前の仕事なのだと教え込まれたら、殺す側も、殺される側も、じっさいにその仕事をやり遂げてしまうほど従順で愚かなのだ。
p.36
彼らは予定調和にしか人生の喜びを見出せない人種なのだから……じっさい大蔵省の職員は、大臣となった政治家に対してどこかよそよそしかった、
---------------------------------------------------------------
p40
人間の印象をすり替えることを可能にしたテレビという機械は偉大な発明だと、彼女は思った。いかなる人生も、表側から見えない、か細い支えによって、かろうじて持ち堪えているものだ……
p119
七歳の少年にとってみれば、追体験のための旅が既に始まっていた、それはテレビの映像や新聞の写真、子供雑誌のイラストでのみ見たことがある乗り物や建物が本当に存在することを、自らの目で確かめるという作業に他ならなかったわけだが、
----------------------------------------------------------------
p44
好意か、もしくはそれ以上の何らかの性的なメッセージが込められていると解釈したとしても、無理はないのかもしれない
p135
ホステスという呼称が示唆していたような、淫らな性的な妄想が、外国人ホステスの、大柄で健康そのものの肉体へ向かうよう、日本人を駆り立てていたという可能性は考えられないだろうか?
----------------------------------------------------------------
p45 (後半の横井庄一につながる記述)
気候の厳しさが、人間が怠惰と享楽の罠に陥ることを未然に防いでくれているように思われたのだ。
p48
京都を訪れるのは高校の修学旅行以来だったが、どこをどう歩いても、見憶えのある景色にばかり出くわした、
鳥獣戯画p19
まださして長くもない小説家としてのキャリアの中で、幸いにして七冊の単行本を刊行することができた、小説中の登場人物が京都の町を訪れる場面は、今まで少なくとも四回は書いているはずなのだが、じつをいうと作者である私が京都を訪れたことがあるのは高校時代の修学旅行のときのたった一度だけだ。いや、会社員になって五年目の夏にも一度、取引先のカナダ人夫妻を祇園祭に案内したことがある。それは会社員生活二十八年間でもっとも屈辱的な、徹底的に悪意に打ちのめされた記憶として、これからも私の中に留まり続けるだろう。
p49
二十代半ばの、人生でもっとも孤独で臆病な時期に、そんな剛毅な女性が目の前に現れたならば、どんな男性でもあっさり平伏してしまうものだが、彼の場合はやはり、高校時代の初夏の夕方の、饅頭屋の店先でのあの異常な出会いの時点で、自分の人生の行き着く先は決まっていたのだという諦念の方が勝ったのだろう。
p54
「痒みが治まらずに眠れないのだが、どこが痒いのかさえもはや自分では分からない、身体が乗っ取られたかのようだ……」電灯も点けぬまま真っ暗な中で話す妻の様子は、けっして取り乱していたわけではなかったのだが、彼を不安にさせた、
p57
積み重ねてきた時間が、過去が、我々を守ってくれるのです
p66
鹿児島の義母からときおりかかってくる電話で伝え聞くよりも遥かに正確で、具体的で専門的で、最新の情報が、マスコミを通じて父親にはもたらされていたのだが、
p77
この子たちだけではなく俺だって、これから死に至るまで、五つ子の父親であることからは逃れられない……三十手前にして、気が遠くなるほどの長い余生が始まってしまったようなものなのだ……「五つ子に限らずどんな人間だって子供が生まれれば、その人は親であり続ける以外の選択肢など持っていないものです」
p80
何といってもこの五人の誕生は、日本じゅうの多くの人々にとって、その年号と共に思い出される記憶の中ではほとんど唯一といってもよい、覚えず笑みのこぼれるニュースだったのだ。
『電車道』p.252
彼からしてみればこれは、最近起こった中では唯一の愉快な事件だった。事件そのものが馬鹿げていたし、金儲けが目的ではないし、何より人が一人も死んでいない、こういう事件が現実に起きる限りは、今の時代もまだ捨てたものでもないのかもしれない……
p83
そんな時代であっても、後の時代に比べればまだまともだった、不愉快な思いに苛まれずに済んだ、そう思えてならないのは、けっきょくこの国は悪くなり続けている、歴史上現れては消えた無数の国家と同様に、滅びつつあるからなのだろう、いかなる国家も、愚かで強欲で、場当たり主義的な人間の集まりである限り、衰退し滅亡する宿命からは逃れられない、我々は滅びゆく国に生きている、そしていつでも我々は、その渦中にあるときには何が起こっているかを知らず、過ぎ去った後になって初めてその出来事の意味を知る、ならば未来ではなく過去のどこかの一点に、じつはそのときこそが儚く短い歴史の、かりそめの頂点だったのかもしれない、奇跡のような閃光を放った瞬間も見つかるはずなのだ、それはわずか半年余り、百八十三日間だけ我々の前に姿を現し、その後は朽ちていく醜態など晒すことなく、ただ一つの建造物を除いて、後腐れなく取り壊され、潔く元の更地へと戻った。
p169
こういう面白い事件、後の時代であればぜったいに起こり得ない、人に語って聞かせたくなるような事件がじっさいに起こった分だけ、やはり当時の世の中はまだまともだった、そう思いたくもなってしまう、核エネルギーの平和利用は可能であると主張し、交通事故死の急増も繁栄のためには免れ得ない犠牲と諦めていた、有機水銀化合物をそのまま海に垂れ流しても希薄化されるのでさしたる問題はないと信じ込むほど、我々はじゅうぶんに無知で、蒙昧ではあったが、自分たちの理解を超える事象に対してまで恥ずかし気もなく知ったかぶりをするほどは、傲慢ではなかったということなのか?
p94
万策尽きた、時間切れでいよいよ放棄するしかないかと諦めた、次の瞬間に、かろうじて生き長らえることが許される、明日への逃げ道が見つかる、その繰り返しだった。
p97
人生を擦り減らすほどの労力と、幾昼夜もの時間を費やし、家族への愚痴と八つ当たりを繰り返しながら、何とかして打開策を探り当てねばならなかったのだが、
p118
だがこれから少年が歩む長い人生においては、何度かは、夢とも見紛うそうした奇跡を目にすることだってあるのかもしれない、
柳田国男『妖怪談義』
少年時代の柳田国男が、布川の兄の家にあった祠をこっそり開けて石の玉を見た後、白昼に星を見る。
「そうして自分だけで心の中に、星は何かの機会さえあれば、白昼でも見えるものと考えていた」
p120
このときでさえ少年は、不思議な既視感を覚えていた、夢の中で見た光景などという借り物の説明では足りない、薄々気持ちのどこかでそうなのではないかと思っていた通りのことが、現実に、次々と起こり続けていた。
p122
「ターン・ライト!」父親はその方向に右手を差し出しながら、不自然なまでにはっきりとした発音で応じた、勝ち誇っているかのような甲高い声だった、後にも先にもこのときほど強く、少年が父親に尊敬の念を抱いたことはなかった。
『金太郎飴』p245
父は即座に「野坂昭如!」と叫んだ、まるで勝ち誇っているかのようだった。なんて凄いんだと私は思った。会社で出世したときも、若くして一軒家を建てたときにも父を凄いと思ったことなどなかったのに、この時ばかりは心の底から尊敬してしまった。
p128
だが地球が公転し、上空の大気が循環している限り、どんな異常気象だって永遠に続くことなどあり得ない、
※「やまない雨はない」という話ではなく、異常はありえるが異常が続くことはありえないという(小説?)倫理のようなものが現れているように思える。異常の終わり。横井庄一が帰ってきてからの生活の方が異常に思えるように、異常の持続、反転、ハレとケ。→「長く不思議な生涯」
この作者の小説では、あらゆるものが容易に反転する。反転を目指して過剰になる。アナキズムを追求するための具体的行動、示威的(?)語り口。
p139
そんな都合のよい変化ばかりが起こるとは思えない、思えないからこそ、それは予見に対する裏切りとして、現実として、時間の延長線上できっと我々を待ち受けているはずなのだ……
----------------------------------------------------------------
p132
この時代の日本人にはまだ、多くの人間が集まる場所ならば、そこにはきっと金と労力を費やして、多少の犠牲を払ってでもじっさいに訪れるだけの価値があるに違いないと、自ら進んで信じ込むような無邪気さが残っていた。
『柳田国男全集2』p553
我々の同胞は、書物の知識を崇拝したと同じように、上流社会の芸術と趣味とに、いつもいたって無邪気な尊信を抱き、これがいい景色なのだよと教えられると、そうですかといって感心する気味があった。なぜいいのかというようなことが、なるべく言わぬようにして、毎度見ているとだんだん人によいのがわかって来るだろうなどと、人の好い考え方をしている。
p146
そこで初めて、流氷に太い脚を侵している、巨大な生物の存在に気がついたのだ。八頭の、本物のインド象が水浴していた、長い鼻で大量の水を吸い上げ、一気に吐き出して自らの背中を濡らすと、その硬い皮膚は、午後の日射しを受けて銀色に輝き始めた。
これは目玉男が六、七歳のころの記憶だから、姉は九歳か十歳の小学生だったということになる、後から調べてみると、このとき見たのは常盤公園で催された、世界動物博覧会に展示された象だったようなのだが、その象が石狩川で水浴していたのは真夏のはずなので、フキノトウを探しに行った春の記憶と、どこかで混ざり合ってしまったのかもしれない。
-------------------------------------
p52
しょせんはこれもあなたが自分で蒔いた種でしょう?
p138
以降何百年も続く災厄の種を蒔くために、このときから血税を使い始めてしまったということではないか!
p156
過去のどこかの時点で、彼らの怒りの種を目玉男が蒔いているはずだ
--------------------------------------
p164
「けっきょく皆がちやほやする新しいものなんて、金の匂いがするから人が寄ってくるだけで、価値を反転させる新しさがあるわけではない」
p173
勝ち目のない、孤立無援の戦いの中にこそ、生気に満ち満ちた時間があり、芸術もそこで生まれるはずだ、その信念だけを寄ってすがる杖として、今まで生き長らえてきたのだ。
目的を達成するためであれば手段において妥協すること、権力や資本家におもねることは、何ら恥ではない……芸術家の犯した過ちは、後の時代の作家や音楽家、建築家、映画監督の犯す過ちの雛型となった。
p176
「あなたは男の子なのだから、一度決めたことは、そう簡単に諦めてはいけない」
p177
けっきょく世の中には、人間を落胆させ怯えさせる仕組みができ上がっているのだという諦めの気持ちしか起こらなかった
p178
一羽の小さな鳥でさえも、群れを作らず、孤独に、自らの本能と肉体だけを支えとして生きていけるのであれば、人間である自分も、たった一人で、世間との付き合いを絶って、金の力なんかに屈服せず、過ぎ去った時間に守られながら生きてゆけないはずがなかった
p222
洋服屋を再開しようとも考えたが、周囲から止められてしまった、この三十年の間に、背広やシャツは採寸して、布地を選び、わざわざ仕立てる物ではなくなり、デパートへ行けば、自分に合ったサイズの既製品を簡単に購入できる物に変わっていた。
『世紀の発見』
「いまではまったく信じがたい話だが、私たちはついこのあいだまで花は花屋で、肉は肉屋で、服は仕立屋で買う世界に住んでいた」
p224
金を稼ぐためだと割り切って、上手く立ち回っているつもりだったが、けっきょく蝕まれていたのは、こちらの方だったということではないか……
『鳥獣戯画』
凡庸さは金になる。それがいけない。
p230
歯向かえない相手は、女性ではなく金、金の力、財力なのだ!
p231
経済的な貧しさと不幸を混同している、薄っぺらな人物としか思えなかったのだが、視聴者の要望に媚びるような単純な造形をされていることも間違いなかった。どうして皆が皆、これほど金のことばかり話題にして、金を稼ぐことを人生の第一義として生きるようになってしまったのだろう?
p229
「戦争というのは、じっさいに行った人間でなければ分からないものです。お話として、伝聞として、一千回聞いたところで、分からないものは分からない、伝えられないところは伝えられない、そういうものです」
p244
世の中の興味関心が薄れ、忘れ去られた後でも、虚構ではない現実の人生は途切れることなく続いている、この日の出来事はその証明に他ならなかった。
p50
「しかし肝炎の治療で入院したはずなのに、どうして産婦人科で診療を受けたのだろう?」
『五つ子』p92
「ほぼ、一年余の療養で元気になった妻は、京都第二赤十字病院の医師の紹介で、京都府立医大の産婦人科に通院した。何度かの検査をうけたと妻は「排卵がおこりにくいらしいの」と言い、排卵をおこす治療をうけることになった。」
※直前に孫の顔が見たいと母が言ったという記述はあるが、確かに、産婦人科に通院する理由がよくわからない。当然、何らかの会話や相談はあったはずで、推測もできるけれど、本のコンセプトや時代のせいもあり、記述としては書かれていない。その余白が存在することで、おもしろい「小説」のように読めてしまう。五つ子のことに限らず、こういう話の鋳型にある隙に、語り手の意志(思)=語り口をつめこんでいくという方法で、この小説は書かれたように思う。そして、語り口が鋳型を侵食する。
順列組み合わせ
五十一万回に一回
p59
「昨日体重を量ったら五十四・五キロでしたから、今の私は十五キロの重りをぶら下げながら生きていることになります」
『五つ子』p125
「五四・五キロ。妊娠前四〇キロ弱でしたから一五キロの荷物を常時かかえていることになります。」
Q、「荷物」を「重り」に変更する時のこと(その時のことでも、今考えることでもよいが、何が反映していると自身思われるか)
p64
「今、お腹の左下がしくしく痛むのですが、これはいよいよやってきた陣痛なのかしら? いやいや、それが違うのです。昨日の晩、父があの懐かしの、和田乃屋の蒸し饅頭を四個も買ってきて、そして自分でも驚いたのですが、高校生でも二個食べればお腹一杯になるあの饅頭を、私は貪るように、一気に四個平らげのです」
※蒔いた種の変奏?
子供の名前が、「智子」だけかぶる(本当の五つ子と同じ)。五分の一。
名づけのタイミングが、四子が壊死性腸炎となった後になっている(実際は名づけの後)。この変更によって、人間が名前のないまま生死の境をさまようという状況が現れてくるが、意図したものなのか。
----------------------------------------------------
Q、女という存在、決定的な出来事や一言
p44
高校生の男の子が突然そんな経験をすれば、その意味について、あれこれと考えを巡らせるものだろう、好意か、もしくはそれ以上の何らかの性的なメッセージが込められていると解釈したとしても、無理はないのかもしれない、それ以降しばらくの間、全校集会や休み時間の廊下、最寄り駅の改札で、彼の視線はその女子生徒の姿を追っていた。
p150
「あなたは男の子なのだから、そう簡単に反省してはいけない」女の姉がそういうのだから、それは男も女も関係ないことは明らかだった、まだ思春期に入る前の、人間がもっとも無防備な時期に、どうにも返しようのないこんな文句を突き付けられたら、だれしもその文句を発した人間の影響下に置かれてしまうものだろうが、目玉男の場合もまったく同じだった、幼い頃にも増して、目玉男は姉の存在を仰ぎ見るようになってしまった
p230
今後三百年は続くであろう、男性が女性に歯向かうことは許されない時代の到来を感じたのだが、戦前の教育しか受けていない彼にとっては、それはこれまで何千年か続いてきた、女性が男性に逆らえなかった時代の映し鏡のようにしか思えなかった。しかしよくよく考えてみれば、それも的外れなのだ
-----------------------------------
Q、読点の付け方
p109
ある朝、職員が挨拶するなり、スコップの柄で鳩尾を突かれて、ぬかるんだ田圃に落とされた、それは悪意など毛頭なかったのだが、たまたま振り向いた拍子に、勢い余って当たってしまったかのように装われた、明白な暴力だった。
-----------------------------------
Q、山本富士子?が松下幸之助の別宅にいたのはなぜか。『千里への道』に書いてある? 創作?
-----------------------------------
p179
つまりそのとき目玉男は、自分は大人の振りをしている七歳の子供に過ぎないことに初めて気がついたのだ。
※八歳の時に姉が死んだから、姉に頼っていた「七歳の子供」であるということ? 万博に行く千葉の少年と重なっていく。テクスト的な紐帯。
-----------------------------------
Q、万博に行く「千葉の七歳の子供」は、父親の描写も含めて自分と重なる部分があると思うが、他の史実の人物を小説に取り込むことと、自分に近いものを小説に書くことの間に、何か違いを感じるのか。その感情が、語り口に影響を与えていると自覚することはあるのか。
Q、プランと制度について
目玉男が姉を殺した自動車社会を恨む場面p152で、コルビュジエの主張を思い出した。コルビュジエは『伽藍が白かったとき』でこう書いている。
第五問――建築の将来をすべて考慮にいれた上で、問うべき基本的な問題は「どんな経済組織が支配的となるか」ということだとお考えになりますか? もしそうだとすれば、最も建築が栄えるのはどのような経済組織のもとですか?
この質問は、建築と都市計画のたゆまぬ研究の結果、私が、今日の騒がしい混沌とした生活の中できわめて明確な原理と態度をもって答えるにいたった観念に触れています。すなわち、
プランは絶対的な主権を持つ! ということです。各人はその専門において新しい時代に適応したプランを作り、それによって彼自身が問題を探ってその奥底を究め、物質的にも精神的にも明日から直ちに実行できるものを知るのでなければなりません。このすばらしい実り豊かな準備の仕事――プラン――こそ、あらゆる質問に答えるものであり、またとるべき手段や作るべき規則、有益な場所に配すべき人間を示してくれるものです。今日どこの国においても、重なる悪に答える同じような哀訴――「法規をもたない……、規則に反する……、所有権にぶつかる……、新しくても強くても真実であっても、考えるだけ無駄だ……、周囲の事情が許さない……」が聞かれます。
それゆえ周囲の事情を告発しなければなりません、しかも正確に。そしてそのためには、現在の不幸を即座の幸福となすものの技術的に実現しうる明確なプランを紙の上にたてる、という楽天的な行為を認めなければなりません。
こうしたプランが作られれば、議論は終り、疑いは払われ、「次になしうることはこれだ」という確信が生まれます。ニューヨーク、シカゴ、パリあるいはモスクワはこうなるべきだという確信です。プランより先に制度が構想されるのであってはなりません。今日われわれを圧潰しているもの? それはプランより先に構想された制度です。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ソヴィエト、その他どこでも、主義の違いや対立はあっても、いたるところでプランを欠くための(滑稽な軽業的な弁解や口実とともに)混乱や過ちばかりです。技術者はその務めを果していません。制度は(それがどんな制度であっても)事実に精通していないのです、自らどこに行くのか(われわれに関係する領域において)知らないのです。火星から見ればそれは、原料を入れないで空廻りする機械に見えるでしょう。機械文明時代の施設のプランが立てられていないのです。
私の行動の基準は、プランの地盤に立つことです。その上に足を踏んばって私は、どのような改革が必要であり、どのような行為をとるべきかを静かに断言できます。プランは、個人的自由の欠くことのできない恩恵を確保し、集団的な力を獲得し、現在の都市集落の気違いじみた浪費を止めさせるために、共同体的な企画を実現する準備をしなければならない、ということを証してくれます。それに、過去の偉大な時代にはみんなそうしたのではないでしょうか? 今日の違うところは、怠慢と利己心に苛まれる幾百万の人々を不幸から引き離さなければならないということです。住宅を建て、都市の細胞を改造し、国に施設をすること、これがなすべき務めです。これが、機械文明の新しい時代の社会のプログラムです。ここに始めて、「食卓の上にはいつもパン」があり、万人のための仕事があり、あらゆる国々の総体的なプログラムがあるのです。
(ラ・ファイエット号にて、一九三五年十二月十八日)
コルビュジエのプランは社会の中で上手く実現したとは言い難いけれども、人類史を考えるきっかけにはなるかと思う。
社会が大きな変革を見ない場合、制度は整うかはともかくとして増えていく。日本では、最後の大きな変革は敗戦時だといえる。この小説には、それから三十年ほど経って制度が整いつつも一方では無法ともいえる過渡期を生きた人々が、制度に対して抗ったり飲み込まれたりする姿が書かれている。
蒙昧前史というのは、蒙昧になる前の歴史という意味とも、蒙昧の始まりとも捉えられるが、制度が増え張り巡らされる過程で、その都度のプランがへこたれていくというのが自分のイメージ。そこでは、コルビュジエが言ったように「制度」が先になってしまう。
そして、制度が張り巡らされている場合、決定と進行は妥協の連続とならざるを得ない。当然、時代は「蒙昧」へ進んでいく。
前田昭夫『千里への道』
ファイトとバイタリティのかたまりのような岡本太郎氏が、「総妥協」の見本のような万国博の事業のなかで貫き通した芸術性は彼の体当り的な行動力のたまものといえるであろう。
『日本蒙昧前史』では万博の用地買収の話が20ページにわたって続いていて、これは住民のささやかな生き方のプランと、制度に後ろ盾を持つ自治体のつばぜり合い。その最後は、現実では大阪府が「移転費用百万円の上積み」を最後の条件として出しているが、それについて小説では書いていない。むしろこう書いてある。
p114
農民たちとは違い、彼らは金では動かない人々だった、彼らの要求は金ではなく、いわば失われた時間を返して欲しいというものだった
テキストとしては何も気にせず読めばいいと思うけれど、自分はこれを書いた時の、文献情報を選り分けるときの手つきと思いが知りたい(存命の作家にしか聞けないので)。
『日本蒙昧前史』が横井庄一で終わることで、より一層そういうことについて考えさせられた。
自分は孤独ということ、そうあることについてかなり自覚的だが、こんなことですらプランがなければ制度にすぐ飲み込まれてしまう。小説や芸術に対するプランがあって孤独になるわけだが、他人を逆恨みするようなプランのない孤独では何かに資するということは難しいように思う。
『日本蒙昧前史』は、後半から「孤独」を巡る人々の話になっていく。目玉男はスタルヒンを思いながら、三島由紀夫『葉隠れ入門』(実際は『葉隠』)を読む。
プランというのは願望によって立つものだと思うけれど、横井庄一が、孤独という願望に気づき、その実現を知るところは感動する。
p191
一日でも早く自立して、誰の世話にもならずに、一人孤独に生きていたかったのだ。
p208
孤立無援の心細さを考えると、両腿の震えが止まらなかった、このとき彼はもう四十台の半ばだったが、年齢など関係なく、子供のように地面に突っ伏して泣き続けた、しかし涙を流しながら一方で、一人になってどこか安堵を覚えている自分にも気がついていたのだ。自分一人になることを恐れながら、けっきょく俺は、夜襲を仕掛けたあの晩からずっと気持ちの奥底で、一人であることを欲していたのだろうか……そしてじっさいに彼らが去って、この洞穴に取り残されたことによってようやく、自分の内なる願望を知ったのか……
p213
もしかしたらもっと以前の幼い頃から、孤独はずっと憧れだった、そして皮肉なことに、故郷日本ではなくこの駐留先の南洋の島で、檳榔樹の根元の洞穴で、孤独はついに実現されたのだ! 人生の目的は達成されたのだ!
---------------------------------------
それゆえ周囲の事情を告発しなければなりません、しかも正確に。そしてそのためには、現在の不幸を即座の幸福となすものの技術的に実現しうる明確なプランを紙の上にたてる、という楽天的な行為を認めなければなりません。(コルビュジエ)
小説家が、史実さえ厭わず即座の幸福のプランを紙の上にたて、現在の不幸という「周囲の事情を告発し」た、そのプランそのものとしての小説――としての『日本蒙昧前史』。