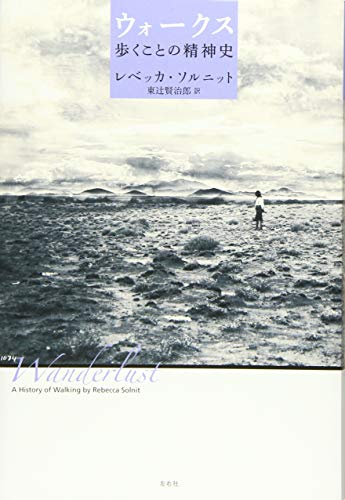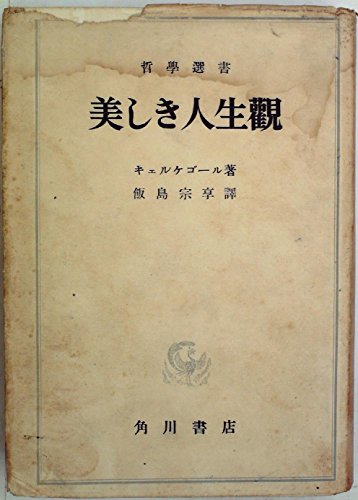歩行の歴史――あらゆる時と場所、フィールドにまたがって、歩行をしてきた人間どもの記録だが、人間みな歩ければ歩くのだから、その中で、歩くことに特別な意味を見出してきた人々の紹介ということになる。
第一章は、著者が歩くことで主題を得る導入になっているが、第二章ではルソーとキェルケゴールという哲学者たちが紹介される。
ルソーの理想の歩みは、「快適で安全な状況にある健康な人間が自由に」そして、おそらく最も重要なこととしては「孤独」に行われるものだった。ルソーは自然の中での一人旅を、人生で最も印象深げに書いている。
一方、街を歩きのめし、書きのめしたキェルケゴールは、日記にこう書く。
わたしのような精神の緊張に堪えるためには気晴らしが必要となる。通りや裏道での偶然の出会いによって気を逸らすのである。なぜなら、数名の限られた人物との交流ではまったく気晴らしにならないから。
(p.44)
気が散る街の喧騒の中を歩いて思索と執筆を続けつつ、ここでは詳しく書かないがキリスト教と父親や自分や元婚約者にまつわる懊悩を抱えながら生きていたキェルケゴールだが、ひょんなことから、街の人々の揶揄の対象にされてしまう。
風刺新聞が「丈の長さがちぐはぐなズボンを履いたキェルケゴールを描いてみたり、多数の筆名や文体をからかったり、フロックコート姿で細い脚をした元気あふれる人物として描いた肖像を配ってみたり」したのだった。
そこまで酷いものではなかったようだが、結構な盛り上がりを見せたらしく、キェルケゴールは大いに気に病んだらしい。
わたしをとりまく環境は、汚れたものになってしまった。憂鬱と夥しい仕事ゆえ、気を休めるために群集のなかで孤独でいることが必要だった。しかし絶望だ。それがもうどこにも見つからない。どこへいっても、わたしは好奇心に囲まれてしまう。
(p.47)
自分のデビュー作となった小説で、キェルケゴールの繰り返したこういう「群衆のなかで孤独でいること」を念頭に置き、今もだけれどあれこれ考えていたのを思い出したりもする。
そんな時間を奪われたキェルケゴールは実に気の毒だが、それでもコペンハーゲンの街を歩くことをやめなかったというのだから、やはり歩き方と書き方との共通点はあるのだろう。
ルソーもそうだが、自分が歩き見て感じたものを、その無関係の傍観者としての視点を、書くものに、その形式に大いに反映させているように感じる。
自分もそれを大いに意識しながら歩いたり書いたりしてきたということが、第二章にして改めて思い出されるが、後に続く各章にも、自分なりの歩きの遍歴にも通じる人間や記述が出てきてかなり励まされ、歩みを進ませてくれる本であった。
例えば第八章「普段着の一〇〇〇マイル」に紹介されている、シンシナティからロサンゼルスまで歩いたチャールズ・フレッチャー・ラミスのこんな記述は、自分がそこらを歩いていて、屈託なく、たびたび考えることだ。
わたしが求めているものは時間でも金銭でもなかった。生きることだ。健康に生きるという意味ではない。幸いにもわたしは健康で体も鍛えていた。そうではなく、より虚飾のない心を充足させるひろがりのある生を求めていた。あわれむべき社会の垣を越えて、満足な体と目覚めた心に生きる、胸の踊るような喜びに生きること。……アメリカ人として、自分の国についてあまりに無知だったこと――多くのアメリカ人と同じく――をわたしは恥ずかしく思った。
(『大陸横断の徒歩旅行』)