息抜きに書評を書きためて少しずつ出している。色々済んだ時、本棚を眺めてこれはと目についたものを手に取ってちょっと読んで書いたりして、書けたりして、amazonの商品紹介でも貼り付けようとしたらもう売ってないものも多い。こうなると本代の足しになればというやましい考えから一応つけているアフィリエイトもないようなものだが、例によってこの本も、ネットではどこにも取り扱いがなかった。
はてそんなにと思うほど綺麗で立派で新しそうなものなのだが、目次のうしろに「装幀・綴込はり絵・本文カット/瀬名恵子」とあり、絵本作家デビュー前のせなけいこなんだから古いはずだ。1965年の出版である。
とびらの次に「この本のつかい方」が書かれている。いくつか紹介する。
□この本におさめた、えらい人の話、百四十二編は、小さな子どもたちに、たのしんで聞いてもらえるように、わかりやすいエピソードによって、つづられています。
□読んであげる対象は、幼稚園児とか、小学校一年生とかにかぎらず、ひとりでも多くの子どもたちが、おかあさんといっしょに、たのしいひとときがもてるように、五、六歳から十二歳ぐらいまでの、かなりひろい範囲を考えてあります。
□おかあさんがいそがしいとき、八、九歳の子どもならひとりで読めるように、漢字はなるべくすくなくしておきました。
三十四歳でもぜんぜん読めるのは、「執筆には、今西祐行、大石真、大川悦生、神戸淳吉、長崎源之助の中堅童話作家六氏をわずらわしました」とあるように、五十五年後の人間には大御所としか思われない作家たちの力なのかもしれないが、その力も及ばず、自分の持っている本には、前の持ち主だった子どもの落書きが残っている。赤鉛筆を本ののどに突っ込んで塗りつぶした跡だ。
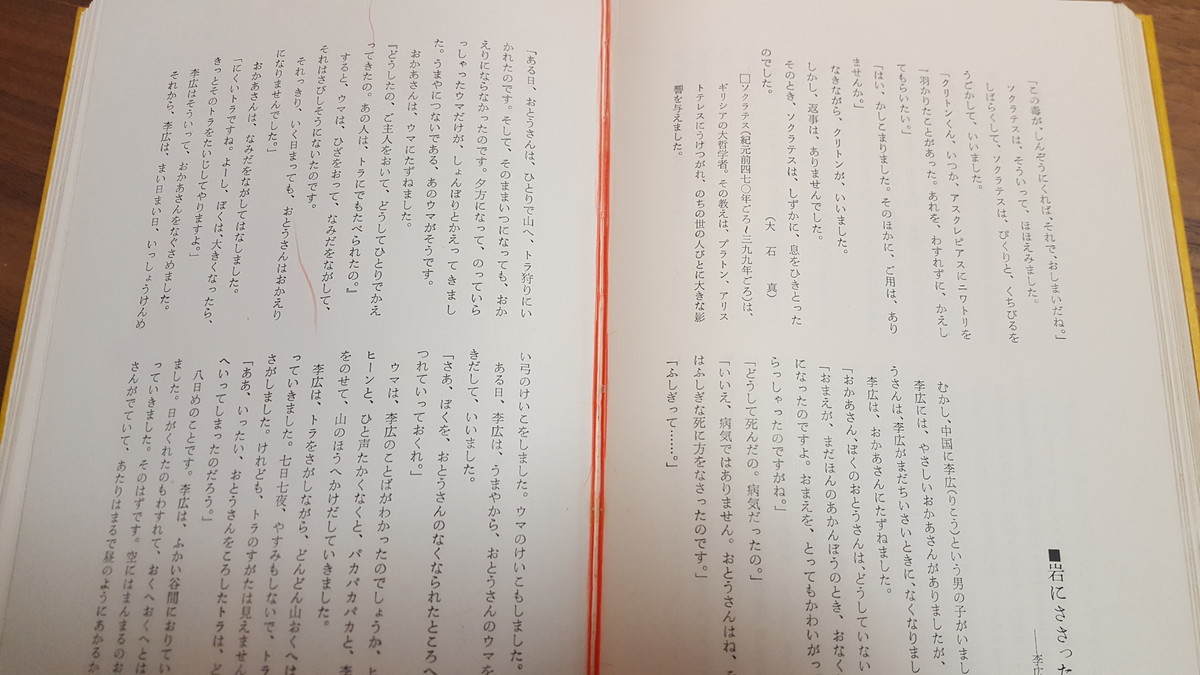
このページで気が散った理由があるのかも知れず、もしそうなら何がと右側のページを見ると、ソクラテスが死んでいる。『チョコレート戦争』の大石真の手による「きまりをまもって、毒をのむ」という話だ。
「この毒が、しんぞうにくれば、それで、おしまいだね」
ソクラテスは、そういって、ほほえみました。
しばらくして、ソクラテスは、ぴくりと、くちびるをうごかして、いいました。
「クリトンくん、いつか、アスクレピアスにニワトリを一羽かりたことがあった。あれを、わすれずに、かえしてもらいたい。」
「はい、かしこまりました。そのほかに、ご用は、ありませんか。」
なきながら、クリトンがいいました。
しかし、返事は、ありませんでした。
そのとき、ソクラテスは、しずかに、息をひきとったのでした。(p.174)
ここで、「アスクレピアスにニワトリを一羽かりたことがあった」というのは、原典である『パイドン』から語を落とさずに直訳すると「我々は治癒の神アクスレピオスに借りがあるから、その借りのために雄鶏を一羽供えてくれ」というような意味の箇所で、昔から解釈の分かれるところである。
フーコーがエイズで亡くなる1984年の講義『真理の勇気』では、フーコーの解釈の過程で、それまでの解釈が紹介されていて助かる。ラマルティーヌ、ロバン、バーネット、ニーチェ、オリュンピオドロスなど、それらの基本的な解釈を大雑把にまとめると、「生きていることはそれ自体一つの病であり、死はその病の治癒であるので、この病から解放してくれるアスクレピオスに感謝の意を示すため、捧げ物をするようクリトンに伝えた」というものだ。
その頃のフーコーの講義は、数年来「パレーシア(率直な語り)」という概念を中心としたものになっていて、政治的舞台で忖度なしに真理を語る政治的パレーシアから個人が胸に抱く倫理的パレーシアという解釈の中で、自分について真理を語るということを考え続けていくものだった。
死期の近いフーコーがやり続けていたことをざっと書くのもなんだが、そこで重要になるのは、主体と真理の間には権力や他者が作用しているということだ。じゃあ他者がなければ真理を語れるかと言うとそういうことでもなく、古代ギリシャにおいて真理を語るためには、例えばソクラテスにとってのクリトンのような、パレーシアを頑張っている他者がいなければならなかったようだというのがフーコーの気づきであった。
こういうことは、マスメディアでは権力や他者によってパレーシアが規制されまくり、SNSでは他者や権力を無視していれば真理を語っているかのような言説が増長しているのを見ると、なるほどなと思う。
で、それを経由した上で「アスクレピオスにニワトリ」のフーコーの解釈はどんなものか。デュメジルを援用したその解釈を読んでいると、デュメジルが三島の死を評価していたことなども思い出されて、点と点が繋がったようでけっこう感動するが、そういう余談はなしに、どうにか理解しているところを簡潔に書く。
まず、他の誰でもなく「クリトンくん」が呼ばれていることを考慮しなければならない。クリトンはソクラテスに死刑を前に脱走を提案した弟子で「我々がソクラテスを救おうとせず手をこまねいていたと非難を受けるとしたら、ソクラテスとその友人たちは世論によって恥辱を受けることになるだろう」みたいなことを言って説得しようとするが、ソクラテスは「善悪について、正義と不正について、すなわち自己に関わる魂が問題になる時、自己へ配慮せず、それについてよく知らない世論に従ってどうする。魂が損なわれるだろう」と諭す。「魂を損なわせないためには、万人の意見に配慮せず、自己への配慮に専心し、そのために善悪や正義と不正について決定する真理に従わなければならない」
この話に着目したことで、ニーチェとかが言っている「病」というのは生きること自体ではなく、善悪など自分の魂が問題になっている時に聞こえてきて、それに身を委ねれば魂を損なわせるような、「パレーシア(率直な語り)」を頑張っていない万人の意見、ひいてはそれに従ってパレーシアを放棄することなのではないかということになる。
この病は、自己に専心し、自己自身に対する心遣いを持って、自らの魂がいかなるものであるか、そしてそれがどのようにして真理と結びついているのかを知ることができるとき、治癒することの可能な病です。
(慎改康之訳『真理の勇気 コレージュ・ド・フランス講義 1983―1984年度』p.141)
脱走について考えたことで、世論を自分の行動に引き入れようとした「我々」の魂がやわになりかけたけれども、パレーシアを頑張って「我々」同士で議論した結果、万人のことは考えず、自己自身に専心することで真理に従って自ら死を選択し、その通りに「この毒が、しんぞうにくれば、それで、おしまいだね」のところまできた。私の死をもって、どうやら「我々」の魂は治癒するということで間違いなさそうだし、アスクレピオスに感謝するためのニワトリを捧げよう、というわけだ。
「クリトンくん、いつか、アスクレピアスにニワトリを一羽かりたことがあった。あれを、わすれずに、かえしてもらいたい。」
当然、これを聞いたか読んだかした子どもは、そんな風に思わなかっただろう。だいたいフーコーの講義は本書の出版から19年後に行われる。
子どもたちは、ソクラテスはアスクレピアスという人物にニワトリを借りたことがあったので、返しておいてとクリトンに頼んで死んだんだなと思っただろう。死ぬ間際にそんなことを言うのが気に食わなかったのかも知れないし、いきなり知らない人物が出てきてニワトリを借りるとか返すとかわけがわからず興を削がれたのかも知れないし、もしかしたら律儀な人だと感動したのかも知れない。その行き場のない気持ちが赤鉛筆を走らせたのかも知れない。
とか書きながら、別に何も考えていないし読みもしないで、偶然、この見開きに赤鉛筆を往復させたというのが一番可能性が高いと思っている。
でも、とにかくそれをしたおそらく子どもがいて、その前に子ども向けでも最期の言葉をはしょることなく書いた大石真がいて、多分その二人の後にフーコーがいて、その人達よりもっとずっと前にソクラテスがいた。
それで、今のところ一番最後に来た自分が赤い線を見てこんな文章を書いている、それはまあ確かに「たのしいひととき」という感があるのだった。



