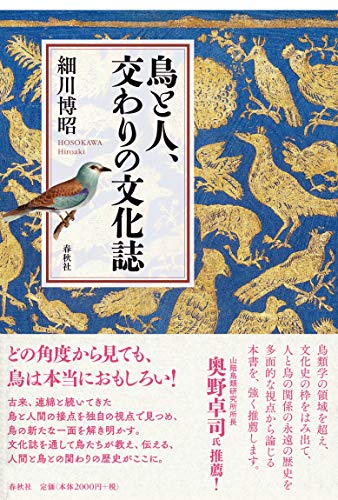『大江戸飼い鳥草紙 江戸のペットブーム』細川博昭
本書はその名の通り、江戸時代の鳥飼いの流行について書かれている。
そもそも江戸時代、鳥は今よりもっと身近な存在であった。森林から断続的に残されている木々を伝って、野鳥が市中に頻繁に姿を現していた様子も紹介されている。
この本に書かれたものではないが、シュリーマンの幕末の日本滞在記では、現在のありふれた光景が、異なる統治体制の中で百五十年前にもあったことを確かめられる。
江戸城の堀に沿った美しい道を進んだ。堀にはつねに、数えきれないほどの雁や野鴨などの野鳥が群をなして集まっている。鳥たちはここならまったく安全であることを知っていて、いかにものびのびしている。この堀の鳥を殺すのはもちろん苛めただけでも死刑に処せられる。
そんな状況で、鳥を飼うことはさらにポピュラーなものだったという。
主にその姿と鳴き声を楽しむためという名目で飼われた数は、世帯数からの割合からすれば今の比ではなく、多くの軒先には鳥かごがぶら下がっていたというし、もちろん飼育用の鳥を販売する業者も数多く商っていた。それが沢山出入りした愛鳥家の曲亭(滝沢)馬琴なんかは、多い時には百羽近くの多種の鳥を飼った。『馬琴日記』には多くの鳥の話題が出てきて、飼育の苦心と楽しみを見ることができる。
江戸時代の鳥の飼い方は、もちろん科学的に間違っていたものもあるが、逆にその多く、例えば糞からの健康診断法や各種不調への対処法などは概ね正しく、鳥ごとの特徴を考慮した鳥かごや止まり木、文鳥などが使う壷巣なども、この頃からさほど形を変えずに今に至っている。
当時の「鳥の飼い方」のベストセラーに、泉花堂三蝶の『百千鳥』という本があった。特筆すべきは、その「序」が、本来は野生に暮らす鳥というものを飼育するにあたっての倫理について書かれているという点だ。
『百千鳥』の「序」は、「予壮年の頃より、小鳥を好て常の楽とす」という文章から始まる。だが、それに続くのは、籠の中に入れられた鳥は苦痛を感じているに違いないと指摘する人間がいる、という記述である。
それに対し、反論する形で泉花堂三蝶はこう述べる。
「野鳥は寒さを逃れることも、雨風を逃れることもできない。餌や水に困ることもあり、鷲や鷹に襲われることもある。羽が抜け変わるトヤの時は、フクロウやミミズクなどにも怯えなくてはならない。だが、籠で飼われる鳥は寒さ暑さを心配することもなく、餌や水の心配もいらないではないか」と。
そう述べた上で、だが、と彼は続ける。「飼い鳥は適切な飼育がなされなければ、命を縮めることになる」。その言葉の裏には、野鳥より短い命になってしまうのなら、飼い鳥になった意味がないという思いが隠れている。そして、「だから私は、人に飼われる鳥が不幸にならないためにこの本を書くのだ」と泉花堂三蝶は綴るのである。(p.154)
著者は、「人に飼われるのが鳥にとっての不幸なら、自分が飼育書を書くことはさらに不幸な鳥を増やすことに繋がるのだろうか。そんな疑問に真剣に悩み、みずからの答えを導き出し、飼育書を書き上げることを決めた人物」だと評している。
確かに、上の文章には、開き直りよりも覚悟のようなものが感じられてならない。
マヂカルラブリーの野田クリスタルは、ハムスターを飼っている。はじめは動物番組に出るためというよこしまな理由で飼い始めたらしいが、今の心持ちは「(平均寿命の)3年間、何も嫌なことが起きないでほしい」というもので、テレビ局に連れていくような仕事も全て断っているらしいと話題になっていた。
「それに比べて」と色々な人が貶められているのも目にしたが、「現代では」「SNSという場では」なんて常套句を言うまでもなく、少なくとも江戸時代から「飼われている動物は不幸なのではないか」という考えはあったし、当人たちにぶつけられていたことを、『百千鳥』の序は教えてくれる。鳥の輸出入も盛んに行われ、珍しさや歌の上手だけを重んじて、野鳥を蔑ろにするような風潮さえあったのだし、ポピュラーな文化だったからこそ、当時から批判は絶えなかったのだろう。
しかし、それを正面から受け止め、深く考えながら、当の動物たちと触れ合い、知識を蓄え、広く伝えようとしている人がいて、彼らはまた、どんなに心を尽くして飼ったとしても、「人に飼われることは動物にとって不幸だ」という文言に反証することはできないと自覚してもいたということも『百千鳥』の序から知れることだ。
逆に、そんな自覚からしか、何も嫌なことがないようやるべきことをやってその生き死にに関わり続けるという覚悟――すなわち「ペットを飼う資格」――は生まれない。だからこそ、泉花堂三蝶は、「飼い方」に先立つ「序」に、それを書いておかねばならなかったのだ。
『神様がサッカーを変えた』岸田光道
フィクションの登場人物の名付けというのはよくわからない。
よくわからないから、付け方もその都度ちがっていて、まあでも実際に名前というものはそんな風につけられるのだから、このままよくわからないままにして、なるべく言わずにおくのが一番よいと思っている。
思っていても、言わずにおれないことが起きることもある。『旅する練習』では、そんなことが立て続けに起こるので、こうしてやたらと書いている。
その登場人物に、那須高みどりという人がいる。
この名前に関しては、やや図式的に考えたものだ。「打ち込むべきものが見つからない」という彼女の潜在的な悩みを象徴するために、そればっかりだが『おジャ魔女どれみ』の主人公の名前をアナグラムにして、音の印象を保存したまま通りを良くすべく段だけをずらす。こういうやり方は、宮沢賢治が擬音を作る際によく用いた方法である。
そうして出てきた「みどり」という名前は、自分に、サッカーに関する仕事にたずさわる一人の人物を思い浮かべさせた。日本代表監督時代のジーコにまつわる著書もある、スポーツライターの増島みどりさんである。
もちろん、密かに字数や音も似せて名字を決めたことなどは作者の問題だ。むしろ、それが外には伝わらないようにという意識の方が働いているから、この名前だけを見てそのつながりを認める人はいないだろう。
だから、その当人によって、その小説の書評が書かれるみたいなことが起こると、面食らってしまう。
しかも、その生業に向き合うにあたって、自らもリフティングの練習をしていたなんて話を読んでしまうと、この小説を書きながら考えていたようなことが、自分の知り得ないあらゆるところで当たり前に行われているという事実の強さにくらくらする。
この世界で、当人のほかには誰も聞かずに弾んだ無数のボールの音に、サッカーに限らないそういう練習の営みに、途方もない気分になり、勇気づけられる。
書評の中で、増島さんはジーコが紙コップを片付ける場面に言及してくれている。(実は、今回の更新は、もともとこの下の文章から始まっているはずだった。上記の出来事が起こったために加筆した)
出版社に出入りしてそんな機会にも恵まれるのだけれど、同じくジーコに取材した経験のある方も、その場面について嬉しそうに話してくれた。取材の際、一緒にテーブルを動かしてくれたというエピソードのあとで添えられた「ジーコってそうなんだよ」の一言が忘れられない。
中田英寿はジーコとの関係について、「監督と選手の関係ではなくて、もっと人間的な付き合いがベースにあるということでしょうか」と問われ、こう答えている。(インタビュアーは増島さんだ)
「そうだね、いい監督に指導してもらったというのではなくて、素晴らしい人間に出会えたな、という喜びが先にある。監督としてダメだとか、いいといった問題ではなくて、僕の人生の中でこんなに素晴らしい人に出会えた、と思えることが何よりなんだ。ジーコと仕事をできたこの3年を通じて一番の感想はそれだね」
(増島みどり『ジーコ セレソンに自由を』p.242-243)
紙コップの場面は、自分がテレビで実際に見たものだが、いつのことだか記憶が定かではない。アジアチャンピオンズリーグのカシマスタジアムで行われたホーム戦のテレビ中継であることは間違いない。2018年の水原三星戦ではないかと思う……セルジーニョがゴールを決めた試合だったというのは覚えているが、セルジーニョはACLのほとんどの試合で得点しているのであまり参考にならないのだった。
ケーブルテレビとかでしか見られない日テレ系のサブチャンネルだし、試合終了後のそんな何気ない場面を見留めた人もそんなにいないと思うが、ジーコが紙コップと荷物を抱えてドアを開ける場面を見ていた人がいたら教えて欲しい。
ジーコとコップというと、こんなエピソードもある。
ジーコが日本にきたばかりのころ、マネージャーの高崎氏がジーコの家でいっしょに食事をしたあとで、食器を洗っていたときのことだった。高崎氏がコップを洗っていると、横にいたジーコがじーっと見ていて、
「高崎さん、コップの洗い方がちがうよ」
といった。
「コップに洗い方があるんですか、どう洗っても同じですよ」
そう高崎氏がいったら、ジーコはこう反論したそうだ。
「NO、先にコップのなかを洗ってから底を洗うのが、順番。この方が洗いやすく、きれいになりやすいのです!」
(岸田光道『神様がサッカーを変えた』p.71)
周囲の人たちはいちいちうるさいなと思うこともあったはずだ。
でも、こういうところがジーコのおもしろさだという気がする。先天的か後天的かはともかく、この合理性とこだわりがジーコの生き方全体に染み渡っている。どのようにサッカーをするかも、どのように生活するかも同じことのように感じられて、それがおもしろい。
そして、そんな人間の影響力が、本人が親近感を抱く文化の行き渡っている日本という国において、最も大きな成果を上げたことも。(ジーコが志半ばで不本意に去ることになった国は少なくない)
共感できる人がいるかわからないが、このおもしろさは、小島信夫が夏目漱石のおかしさについて書いた印象と、かなり近いものだと思える。
『道草』が刊行されたときに、京都の料理屋の奥さんが、まだ本をいただいてませんよ、『道草』を送ってください、と漱石に手紙を出した。それに対して漱石は、もう本は送った、嘘をついちゃいけない、なぜ嘘をつくんですか、それを改めなきゃダメですよ、という内容の返事を出している。その手紙は残っていて、全集にも収められていますけれど。こんなエピソードひとつとっても、なんだかおかしいでしょう。そういうおかしいところがあるからこそ、漱石はいい小説を残せたんです。
(小島信夫『小説の楽しみ』単行本 p.51)
もっとも、小島信夫なので、実際は『道草』ではなく『硝子戸の中』だし、手紙の文面も、前に桜を見に行く遊びの約束をすっぽかされた恨みを蒸し返しつつのめっちゃ早口で言ってそうという猛烈な文なのだが、漱石のこんなところが、その小説と無関係であるはずがないという点では同意できる。
ジーコもまた、約束や契約という言葉に人一倍厳しい。辞めそうになる通訳にも何度もそれを言う。無理強いはしないまでも、「契約したんだろう。お前はプロだよな」と何度も確かめる。
「99.9999パーセント無理」と言われたJリーグ入りを果たした鹿島のため、その創世期から尽力したことも、やり甲斐はもちろん、「鹿島とそういう契約を結んだからだ」とつけ加えることを忘れない。
余談だが、って余談しかしていないが、この「99.9999パーセント無理」というのは、何から引いてくるかで若干の誤差がある。そもそもこれは、当時、Jリーグ加盟に関する実権を握っていた今なにかと話題の川淵三郎チェアマンが、住友金属蹴球団(後の鹿島アントラーズ)のJリーグ入りの可能性について発言したものだ。
色々調べてみると、最も有名なインタビューでは「99.9999」、その後に出された著書では「99.9」としている。新聞記事でも9の数にやや誤差がある。それを言われた鈴木昌をはじめ鹿島側の証言の多くは確率が一番低くなる「99.9999」だが、もともとは厳密にシックスナイン(=ほとんど完全)の意で発言したものではない、揺れのある表現だったのかも知れないという疑念も生まれてくる。
そんな余計なことを考えつつ、また小説のその場面では、まだ特にアントラーズサポーターというわけでもない「私」がその場で補足しつつ考えているという形に留めていたこともあって、細かすぎる「99.9999」を避けたが、その後で、鹿島アントラーズが30周年にあたってこのような動画を出した。
【鹿島アントラーズ】30周年コンセプトムービー「夢の続きを」
こんな感動的なものが出るとわかっていたら、せっかくだからちゃんと「99.9999」にしておけばよかったと思って、少し後悔している。