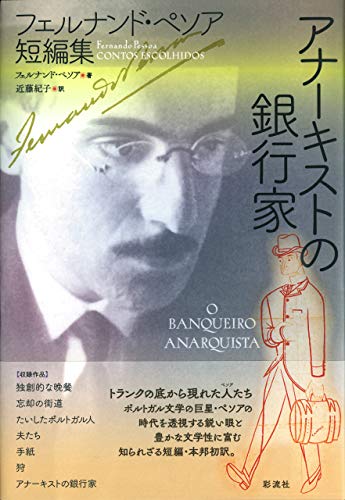『案内係 ほか』フェリスベルト・エルナンデス/浜田和範 訳
最近、あんまり小説を読まないが、これは何度も読み返したし、たくさん書き写した。ピアニストから転身したウルグアイの作家の短編集である。
いきなり個人的な見解を言えば、演奏すること、書くことといった行為の内実にとことん興味があり、全てがそのことに関わるように書いている作家だと思う。その思弁が、それぞれの物語というかそれぞれの「状況」の中にちょくちょく差し挟まれ、だからそんなことを考える由もない人にとってその記述は幻想的や「シュール」といった印象になるだろう。そして、その通りにシュルレアリスムと言って構わない面もある。シュペルヴィエルも讃えているくらいだ。
アンドレ・ブルトンはシュルレアリスムを「口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスム。理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」と定義しているが、そこに範をとっているかのような記述は、そこかしこに発見できる。
私は誰に対しても、特に自身に対して用心したい。まるで十本の指が私をくすぐろうと脅かし、それを避けねばならないかのように。もう一つ用心しなければならないのは、分類するという悪癖だ。秩序というのは手段としてはいいが目的としてはよくないのは確かだが、誰もがそれを忘れ去り、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまうのだ。
(p.269)
フェルナンド・ペソアがもっと小説を書いて、断片に灯る光と光の間に横たわる薄暗さに目をつぶることができたならこんなものになったのかも知れないと思わせるが、そんな推測も、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまった結果にしかならない。誰もが、こんな風に文字が連なることで何かを言った気になっているのだろう。
とはいえ、この前段も含め、こういう自己否定を繰り返している人間の書き物が似てくることは否定できない。彼らが隙あらば行う自己言及は「自分の行為を、その行為の副産物によって否定する行為」で、やればやるほどに狭まっていかざるを得ず、新たな否定の隙もないと思えるほどの狭さ自体によって似てくるからだ。それは書くという行為のどん詰まりである。どん詰まりだが、アキレスと亀の距離のように、永遠に続く有限の中の無限とも言える。
だからこそ、彼らが文を書く上で重視するのは実感である。自己否定に塗れた行為の救いは、自分を否定する能動つまり今まさに書いている時にだけ存在する。書くことが、究極にはそんな行為であることを思い知った人間は当然、何を書いていようと、次の箇所で否定されているようなことに意義を見出すことはできない。
私は意を決し、彼には理解できないことを説明してやった。曰く、私はどこかへ行くかなどまったく興味なしに書いているのであり――たとえそのこと自体がどこかに行くことになるとしても――さしずめ次の目的地は、悦びを引き出し必要を満たすこと以外にない。私の中にあるこの必要というのも別に、何かを教えることになどまったく関心はない。もし私の書くものが結果として、楽しませ感情を揺さぶるものに関心を示しているのであれば、それも結構。だが私は少しずつ埋まってゆくこの素晴らしいノートを埋め、やがて埋まった日にはフルスピードで読んでみるという以外、何もしようとは思っていない。
(p.277)
他人の楽しみや学び、それに伴う賞賛は「結構」だが、「関心はない」のだ。作中人物はノートを埋めて読むだけと言うが、出版社の、精一杯わかりやすい紹介に努めたであろう文を読んでもらえば、書くことについての考えを頭から離さずどう小説にするかについて、相当な関心を持ってあの手この手で「状況」作りに取り組んでいたことがおわかりいただけるかも知れない。
思いがけず暗闇で目が光る能力を手にした語り手が、密かな愉しみに興じる表題作「案内係」をはじめ、「嘘泣き」することで驚異的な売上を叩き出す営業マンを描く「ワニ」、水を張った豪邸でひとり孤独に水と会話する夫人を幻想的な筆致で描く“忘れがたい短篇”(コルタサル)「水に沈む家」、シュペルヴィエルに絶賛された自伝的作品「クレメンテ・コリングのころ」など、幻想とユーモアを交えたシニカルな文体で物語を紡ぐウルグアイの奇才フェリスベルト・エルナンデスの傑作短篇集。
僭越ながら、ここまで書いたことには、自分自身かなりシンパシーを感じる。また一人そのような人物が過去にいたという証拠を集めて、これが出版された2019年の年末はとてもいい気になっていた。
特に次の記述は、そこまで読んできてこの興味深いフェリスベルト・エルナンデスが何をしているか見てやろうと息巻いていた上に、2018年頃の自分が小説という形で実現しようと取り組んでいたことが書かれていたものだから、かなり驚いた。これが客観的偶然と呼ばれるものなら、自分のやってきたことも順調かつ敢えなく狭まってきているのだと思えてまんざらでもない。
親愛なる同業者、そう、そう、今読んでいる君のことだ。ここに並ぶ文字の目、穴、本体のすき間から、尖った角の後ろから見ているんだからな。君も同じことをやろうと試み、二人して文字のあいだを移動する際に武器を隠したりすれば、傍目からは無邪気に隠れんぼでもしているような格好になる。つまずいたらご用心!
(p.263)
『ライ麦畑でつかまえて』J・D・サリンジャー/野崎孝 訳
あちこち出掛けて、博物館や郷土資料館があると必ず入ることにしている。高校生ぐらいからそうで、知識もまばらだったその頃に見たことなんて実際ほとんど覚えていない。松戸市立博物館の常盤平団地の展示とか、小さい頃の記憶が鮮明に甦って驚くこともあるけれど、大体は展示内容なんて記憶にないまま変わったスロープや階段とか、動線だけ覚えていたりして、来たことあるなとだけ思う。
今でこそ、どんな順番で見るかなんて展示物ですぐにわかるが、そんな頃はめちゃくちゃだったろう。今でも、平日に体が空くのをいいことにのんびり見ていると、新たに入ってきた身なりの整った比較的若そうな老夫婦が、甕棺墓の埋葬方法を興味深そうに見たあとで後ろを振り返って、本来ならその部屋を時計回りにぐるっと回った後でたどり着くはずの大和絵を腕組みして眺め、そのまま反時計回りにぐんぐん時代を遡ってきたのとすれ違うなんて場面にはざらに出くわすが、そんなものである。自分も門外の出されるところに出されれば、似たような動きをしてしまうだろう。
こうした博物館や郷土資料館は、もちろん学術を基準とした展示だから、多くの人々にとってはっきり言えば退屈なものとなっており、見ていると皆どんどん素通りしていく。つまり、ほとんどの人には興味の持ちづらいものが広く展示されている。そんなものだろうと当然のように受け取られるが、これは我々が恵まれているのであって、別に当たり前のことではない。
ベラルーシ各地の郷土史博物館の類を見学すると、全体の三分の一か、下手をすると半分近くは独ソ戦に関する展示と相場が決まっている。一般国民の歴史イメージは、だいたいこれに相応しているのではないか。歴史といえば、ナチスの侵略と蛮行→パルチザン戦と勝利→戦後復興という筋書きであり、それ以前のクリヴィチだ、大公国だといったことは吹き飛んでしまっている。
委託先一つで学術に背を向ける図書館だって出るように、人の意識で何もかも変わってしまう。届かぬことは無しにするのが人の意識だ。忘却だって使いようとはいえ、こうした種類の忘却は虚しい。
本来、博物館の全てに行き届くほどの意識というのは人に無く、それぞれに向けられたそれぞれの人の意識がその場の広さに応じて一堂に会し、公共の名のもとに場を譲り合い、あの静かな空間を作っているということを忘れてはならない。
また、それを見るための知識によらず、誰もが入れるのが公共施設というものだ。もちろん、数百円払えれば貧富も何も関係なく、ドレスコードだってない。
岩宿遺跡を発見した相沢忠洋は、浅草の履物屋での小僧奉公をしていた十二歳の時、初めてひとりで上野の博物館を訪れた。それまで「私のような者が行く所ではないような気がして、そのときは塀ごしに見ただけで帰ってきてしまった」こともある中、ある日に思いきって出かけ、「私のような格好をした者は一人もなく、みんなきれいなきものや服をきているので気が引けたが、勇気を出して建物の中に入った」とある。
先日、自分は一年ぶりに栃木県立博物館を訪れた。螺旋状に上がっていくスロープの途中、当地の代表的な自然を一目で把握できるようにしたジオラマがある。右ではノウサギが茂みから飛び出し、左では鹿の親子が向き合っている。手前の子鹿は首をのばして奥の母鹿を見上げ、母鹿は子を見下ろしつつ、その先――つまりはスロープを上ってきた自分のいるこちらへ気を配っているようだ。一年前に見たままである。
そのジオラマの鹿で、本書を思い出したのでこんなものを書いている。
ホールデンは小さい頃に先生に引率されて何度も訪れた自然科学博物館の、いつも変わらぬ姿に思いを馳せる。
いやあ、あの博物館にはガラスのケースがいっぱいあったなあ。二階へ行けばまだあって、水たまりの水を飲んでる鹿が入ってたり、鳥の群れが冬を越すために南へ向かって飛んで行くとこを納めたケースもあった。見物人に一番近いとこの鳥は全部剥製で、針金でつるしてあるんだけど、奥のほうのはバックに絵を描いただけなんだ。でもそれがみんな、本当に南に向かって飛んでるように見えるんだ。でも、もし頭を下げて、下から鳥を見上げるみたいにすると、それがいっそう急いで飛んでるように見えるんだ。でも、この博物館で、一番よかったのは、すべての物がいつも同じとこに置いてあったことだ。誰も位置を動かさないんだよ。かりに十万回行ったとしても、エスキモーはやっぱし二匹の魚を釣ったままになってるし、鳥はやっぱし南に向かって飛んでるし、鹿も同じように、きれいな角とほっそりしたきれいな脚をして、あの水たまりの水を飲んでるはずだ。
(J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』p.188)
こんな場面も、博物館に何度も訪れてそれを見るという経験がなかったら、そこまで感興をそそられるかわからない。そのぐらい、そこでしか生まれ得ない感情が詳らかに語られている。
このあとでホールデンは、何度行っても変わらない展示の中のものたちに対して、見る方は行くたびに変わっていることに言及する。それによって何が示されようとしているかは目下の考え事なのでここで詳しく書かないが、いわば公共の場に置かれるようにして小説に書かれる感情が、言葉ではなく記憶とともに実感できるというのは、読み手にとって深い歓びであるのは間違いない。
何であれ、こうした私とつながる瞬間のために公はあるのだろう。公共は対置される概念である私や個に恩恵をもたらすものであるべきというのが公益の考え方で、もちろん、博物館もそのような目的でそこに建っている。
歴史や郷土のために貴重で意義深いものが保存されているというだけではなく、同じものがいつもその形でそこに置いてあるということがどんな理由であれ個人に何かを思わせる、それだけで公益だと多くの人が考えられるような社会であるといい。いつ来て何を閃くかもどんな感慨にふけるかもわからない個人のために、博物館はひらかれているのだ。
相沢忠洋は、一家離散の上に奉公に出されるというつらい身の上の中でひとり大事に集め、築き上げてきた私を、個を、博物館の中に見出した。それを受けてさらに育まれていった彼の知見によって初めて関東ローム層から発見された打製石器は、今、岩宿博物館のガラスケースの中に収められている。彼が初めて上野の博物館を訪れた時の続きを載せておく。
最初のへやに入ると、ガラスの大きなケースに、埴輪や大きな土器があった。
順路にそって見ているうちに、私は自分の目をうたがうくらいおどろいてしまった。自分が、コウリのなかにもっているやじりや斧とまったく同じ形をしたものが、この立派な博物館のなかにいくつも並べてあったからだった。
私は息をつめて凝視した。
石斧や土器を初めて手にしたときの鎌倉でのことや桐生でのことが、走馬燈のように頭のなかで回転するのだった。
(相沢忠洋『「岩宿」の発見』p.54)