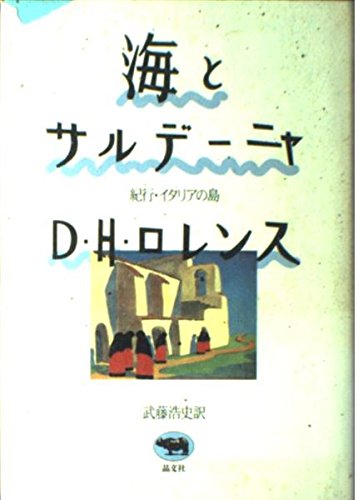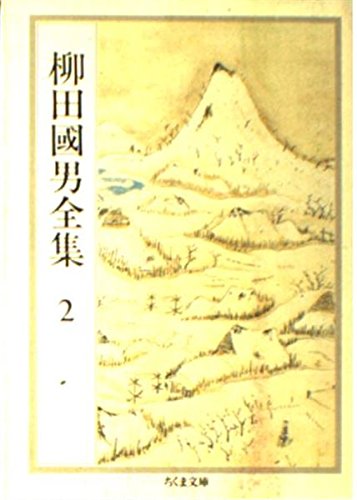『声と日本人』米山文明
何か創作したいと思って、まず人はその創作物から学ぼうとする。映画から映画を、マンガからマンガを、小説から小説を考える。そして、絵画からマンガを、演劇から映画を、お笑いから小説を考えたりする。もちろん、世界に生み出された作品の数を考えればそれだけでもきりがないのだけれど、世界はそれよりもっと広いのだから、創作物から創作物について考えることすら、せせこましい気もしてくる、だんだん。
いくとこまでいった人ほど、その枠を越えたあらゆるものから自分の分野に資するものを得るのに貪欲だという傾向はありそうだ。世の人はそこへ能動的に学ぶ姿勢を見出して感心したりするが、年がら年中一つのことについて考えているから、触れたもの全てをそれに繋げて考えてしまうだけというのが本当に近いと思う。
逆に言えば、異分野から学び考えることができないのは、年がら年中そのことについて考えられないある種の未熟さを表すと言えるかも知れない。もちろん、そのあることで何者かになりたいと思っているなら、だけれど。
異分野のそれとは自分に加える変数みたいなもので、奇特なものだろうと別に構わないが、あんまり好き勝手にやっても、外れるのはいくらでも外れられるのだからつまらない。個人的な意見として、例えば小説について考えることが野放図にならぬよう、一方に文学史や理論があり、自分が有象無象から学ぶべきものを大きく選りわけてくれている気がする。その知識が、縁遠いと思われる異分野に広く目を配る時の命綱となる。
どんな分野でも、そんな感じで使えるものは何でも使おうと、いやな言い方をすれば「役に立つもの」を渉猟していくわけだ。そうやって桑田は古武術を学ぶ。その師である甲野善紀も、まあ快く思わない人もあるだろうが、自分の技を「役に立つもの」として積極的に他分野へ広めている。
本書にも「人体を使って表現するあらゆる行動で、呼吸はその原点になる。各種スポーツ、芸術、その他における例は枚挙にいとまがないほどである」(p.40)と書かれ、あらゆる分野の人々がその専門家である著者を頼ってくる様子が豊富に紹介されている。
自分がこんな本を読むのも、「役に立つもの」かも知れないという期待があることは否定できない。ふつうは今の引用中の「人体を使って表現するあらゆる行動」の中に文学を含めたりはしないかも知れないが、自分は含める。だからそのまま活かすことができると都合よく考えるし、そうでなくとも、転義法が全てを学びに変えてしまうということもある。
人間にとって「生きる」ことは「呼吸(イキ)」ることである。息を吸う吸気によって大気中の酸素の多い空気を体内に取り入れ、体内で不要になった血液中の老廃物を息を吐く呼気として体外に排出する。そしてその排出するときの呼気流と呼気圧を利用して「声」をつくる。この発声をする際の呼気と吸気をいかにうまく、効率よく使いこなせるかという点が最も肝要でしかも難しい課題になる。呼吸は「声」にとって根源的な役割をはたしており、呼吸がなければ声も生まれ得ない。声は排出する不要のガスのリサイクルである。
(p.26)
転義法とは、こういうものを読んで、いとも簡単に次のように考えることができるということだ。
人間にとって「生きる」ことは「書く」ことである。言葉を知ることで世界を認識するための新たな情報を取り込み、その意味では不要になった老廃物を文字として体外に排出する。そしてその排出するときの圧力を利用して「小説」をつくる。「小説」は排出する不要の言葉のリサイクルである。
突飛なことで筋も通ってるんだかないんだか、何言ってるんだと思われるかも知れないが、この文章を読まなければ、およそ思いつかないようなことであるのは間違いがない。正しいとか正しくないとか、そんな問題ではない。
およそ自分を喜ばせる新しさとは、何言ってるんだと思えるけれど関連がないとは言いきれないような何かでしかなく、それは、こうした無理筋の転義法の中で、それ以上解釈の難しい文章そのままの形として多く収穫される。もちろん、元々の文章そのものが興味深いものでなければそんな気も起こらないのだけれど、実際、自分は上の文章について考え続ける意義があると思っている。
本当はそれぞれがこういう少しでも変わったことをどんどん考えて共有していかなければならないと思うが、大半の人が取り組んでいるような創作物から創作物について一生懸命学ぶ方法では、こんな幸運はほとんど起こらないということは、僭越ながらよくわかっているつもりだ。自分も以前はそんな風だったから。
でも、そんな風だった長い時を経なければ、こんなことが自然に行えないことも知っている。じゃあその長い時の道筋はどうであったかということも、転義法を好き放題に用いれば、本書の中にヒントが書いてある。
例外的な境遇は除いて、小説が別に誰にでも書けるのは、歌が誰にでも歌えるのと似ている。しかし、その先で「何者かになりたい」と思うとして、「何者か」と「そうでない者」の違いがどこにあるのか、「才能」と「努力」と呼んでしまっているものをどう捉えるのか。何より、その根本となる「どのように言葉を取り込むのか」について、次の文は多くのことを示唆してくれるだろう。
呼吸の方式は前述のように胸式と腹式に大別され、安静時(声を出していないとき)の呼吸では胸部と腹部はほとんど同時に動く。これを等時性(synchronism)という。このときは胸郭と横隔膜とはほぼ同時に動いている。ところが発声時(話すとき、歌うとき)には同時に動かず、瞬間的なズレが起こる。これまでの内外の研究を要約すると、特に歌う場合、熟練した歌手では腹部の動きと横隔膜の動きが時間的にずれ、同時に動かない。腹部と横隔膜だけでなく、胸部と腹部も非等時性が顕著になるといわれる。
歌うとき、話すときには非等時性がある方が有利だということになる。ある程度パターンのきまっている横隔膜の動きと、かなり複雑な動きの可能な補助呼吸筋すなわち腹筋群(腹筋、背筋、骨盤筋、臀筋、その他)とが同時に動くのは未熟な歌手の証拠だということになる。
まとめてみると、発声時に望ましい呼吸とは
①腹筋周辺の動きと横隔膜そのものの動きとは非等時性がある
②胸部の動きと横隔膜そのものの動きとはほぼ等時性がある
③胸部の動きと腹部周辺筋群の動きとは非等時性がある。
ということになる。
発声のための呼吸訓練をする上で肝要な点は、横隔膜そのものの訓練だけではなく、意識的にコントロールしやすいその周辺の補助呼気筋群その他を使って、間接的に横隔膜の動きを自分の意識下のコントロールといかに結びつけられるかということである。
(p.37)
『海とサルデーニャ―紀行・イタリアの島』D・H・ロレンス/武藤浩史 訳
D・H・ロレンスの小説は長らく読み返していないが、紀行文はよく読む。不死鳥社の全集には四つ収録されていて、それも含めて色んな訳をさがして読んだが、一番手に入りやすいのも親しみやすいのも本書、晶文社の『海とサルデーニャ』であろう。
訳者あとがきによれば、アンソニー・バージェスも、「ロレンスのもっともチャーミングな作品であると同時に、まず間違いなく最高のロレンス文学入門書である」としているそうだ。西脇順三郎もその小説より紀行文を好んで、訳した「イタリアの薄明」が集英社の文学全集に入っている。
当時シチリアに住んでいたロレンスが、同じく地中海のサルデーニャ島へ旅した記録である。「もっともチャーミングな作品」と言うのも頷けるほど、この旅は、当地の人々との微笑ましい交流や憎めないドタバタ劇に満ちている。
実際、旅というのはそういうもので、経験上、予定も決めずに何泊もふらふら歩くような方法で旅をしていると、生活の中とは異なる出会い方で人に出会うし、しばし行動を共にするのは珍しいことではない。現代の日本でさえそうである。
柳田國男は旅行というものが汽車で名所名跡に行って帰ってくるものに変わったと著書で何度も憂えているが、それからかなりの年月が経ち、その印象はますます強固なものとなったらしい。
柳田がその感を強めていったのは、官界を辞めて全国各地をより頻繁に調査旅行し始めた1920年以後だと思われるが、『海とサルデーニャ』は1921年1月の旅行を元にしている。ちなみに柳田は1921年7月にジュネーヴの国際連盟委任統治委員となって渡欧しているので、彼らは同時期に隣国にいたわけだ。
どうということでもないが、興味深い類似が見つからないでもない。柳田が巡った農村と地中海の島ではちがうと思うかも知れないが、今でこそリゾート島のサルデーニャは、当時は「山賊」だけが名物といわれたところだそうである。そこに走る山間鉄道で、名所を巡るわけでもなくロレンス夫妻が旅した十日、それが『海とサルデーニャ』で、つまり、読者のうちに、そこを訪れたことのある人はほとんどいなかった。
柳田は、『秋風帖』にこう書いている。
紀行は全体誰が読むものかということも、今さらながら問題とせざるを得ぬ。実地を知らない人たちへの案内の書であるならば、この本などはあまりにも説明が拙であり、またあまりにも筆が省いてある。あるいは『膝栗毛』のように知っている人々のために、共同の興味を抱かしめるものとしては、私の通る路はいつもやや片隅に偏していた。当時自分ではまだ心付かなかったけれども、やはりわずかばかりの同じ道を行こうとする人の他に、主としてはその土地の住民の、目に触れることを期していたらしいのである。前代の旅日記の類には、こういう読者を予想したものは稀であったろうが、しかも今日となってはこの人たち以上に、深い関心をもってこれを読む者は他にない。紀行の目的とするところは時世とともに変らなければならなかった。私などの観察は精確でなかったかも知れぬが、とにかくにこの新しい需要に応じたもので、それが事実を身(ママ)誤っておらぬ限り、いつかはその土地の人に認められて、あるいは記録なき郷土の一つの記録として遺るかも知れぬ。
(『柳田國男全集 2』p.193)
書こうが撮ろうが何だろうが、これを残したいとか、これが残されてよかったと思うのは奇妙なもので、壮大な景色でなくともハレの舞台でなくとも、そこで起きる全てが興味深いということは十分にある。映画の蓄積の一番下にある『工場の出口』を映した五十秒には、もちろんフィクションの意識もすでにあるが、何よりその動きを映し残すことへの大きな衝動がある。さて新しいこいつで何を映してみようかとなった時に、他でもない自社工場の出口の前に機材を置こうと決心したのだから。
そんな衝動は、今なお死せず息づいて、人を駆り立てている。ただし、その大半の内実――どこでどう何を残すのかという意識や方法は、ますます空疎になっていくようにも見える。自分のために残す限り、人は腑抜けに大きく傾く。己の記憶を補完するものとして何気なく残すのは当人にとっては無論かけがえのないものだが、誰もが発信できる世の中になったんだからと嘯いてご立派な意識でやっているものの大半さえ、名所を訪ねてその写真を撮るのと大差ない未熟な意識と方法でできている。柳田の文を読み直すまでもなく、どこでどう何を残すかというのは一種の企みで、企みなく残されるものは当人の思うほど役に立たない。
ロレンスは明らかに小説とは書き方を変えていて、そこには何をどのように書き残すべきかという企みが感じられる。この紀行文は、前述した通り、共同の興味を抱かしめるものとしては通る路が片隅に偏しており、案内の書としては当地の人々とのやりとりが多く個人的記憶に大きく傾きすぎているが、もちろんそれも企みなのは、実は、サルデーニャを行き先に決めた理由からして明らかだ。
サルデーニャにしよう、何もない場所だから。歴史がなく、日付がなく、民族もお国自慢もないから。サルデーニャにしよう。
(p.14)
さらに、こんなところもある。
ヌーオロには何も見るものはない。じつをいうと、いつものことながらほっとした。名所見物は腹の立つほど退屈である。だが、ありがたいことに僕の知るかぎり、ここにはペルジーノのひとかけらもないし、ピサ様式の何ものもない。幸いなるかな、見所の何もない町よ。なんと多くの衒い、気取りが省かれることか! そうなれば、生は生の本分にもどって、博物館に物を集めることではなくなる。そうすれば、すこしけだるい月曜の朝にせまい道をぶらついて、ちょっと噂話を楽しんでいる女たちを眺めて、パン籠を頭にのせた老婆を眺めて、仕事をいやがる怠け心を起こした連中、勤労全体の潮がうまく流れない様子を眺めたりできる。生は生、物は物。「物」を憧れ求めつづけるのは、たとえペルジーノの作品でさえいやになった。かつてはカルパッチョやボッチェテリに身を震わせたこともある。だが、もうたくさんだ。土くさい白ズボンをはいて腰に黒いひだ飾りをつけた灰色髭の老農夫が、上着も外套もはおらずに、腰を曲げて牛のひく小さな荷車の横を歩いてゆく。ただそれだけの姿、それならいつ見ても飽きることはない。「物」にはうんざりだ、たとえペルジーノでさえ。
(p.237-238)
ロレンスは「見るものはない」と言いながら、実によく見て書いている。全体通して描写は実に細かい。こうなると、むしろ柳田國男との共通点ばかりが見えてくる。およそ百年を過ぎてみれば、これは明らかに同じ企みに基づいた、記録なき郷土の一つの記録なのだ。
1921年のサルデーニャの人間が、当時の文化と環境の中で、それぞれどのように小ずるく、どのように愛嬌をもって、どのように無頼であるいは無知であったかという「生の本分」に忠実な姿を、この本よりも活き活きと書き残しているものは、他にないだろう。
様々な場面で、よくわからないけど泣きそうになり、これもなぜだか知らないが、書き残されるべき場面だったという気がするのは、その書きぶりはもちろん、それを書いておかねばならないと思った、その日その時その場所でのロレンスの衝動が、伝わるからに他ならない。
例えばこんな、移動のバスに乗ったまま、しばらく待たされる場面。
ただただひたすら待つ。すると、豊かな白黒衣裳の老農夫が老人特有の素朴な笑みを浮かべて、うれしそうに乗りこんできた。あとからスーツケースを持った血色のいい青年が乗ってくる。
「さあ!」と青年が言う。「もう車んなかだぞ」
すると老人は素朴な笑みをなおも浮かべて、ぽかんとふしぎそうにあたりを見まわした。「ここならだいじょうぶだ、な?」青年町民君がえらそうにくりかえす。
だが、感情の高ぶった老人は答えない。あちらこちらを見まわす。とつぜん小さな包みを持ってきたことを思いだして、ぎょっとしてさがしはじめた。紅顔の青年が包みを床から取って、老人に手わたす。ああだいじょうぶだ。
小柄な車掌が、裏にウールのついた粋な軍人用短コートをまとい、手に郵便袋を持ってきびきびと大股で小道を下ってきた。運転手も僕の前の運転席に乗りこむ。首にマフラーを巻いて、耳まで帽子を下ろしている。クラクションをプーッと鳴らすと、老農夫は身を乗りだして、興味津々、目を凝らす。
がたんと揺れるといきなり山を登りはじめた。
「ありゃー、どうしたんだ?」
度肝を抜かれた老農夫が言う。
「出発するところだよ」
紅顔の青年が説明する。
「出発! もう出発したんじゃねえのか?」
ほがらかに紅顔君が笑った。
「ちがうよ。乗ってからずーっと走ってると思ったの?」
「ああ、そうさ」と素朴に老人が言う。「ドアが閉まってから、ずっとな」
同意の笑いをもとめて青年が僕らを見る。(p.192)
ちなみに、ここで老農夫が着ている「白黒衣裳」はサルデーニャの民族衣装で、ロレンスはここまででさんざんそれを素晴らしいと褒め称え、多くの若い農民がそれを着ないで「イタリア製カーキ」の服を着るようになったことを嘆いている。
つまり、話は戻るが、ここにはサルデーニャの移り変わりが、バスの車内という象徴的な場において書かれている。便利に変わっていく現実を、民族衣装の老農夫が、ロレンスのようにそれを惜しむ意識などもちろんなく、訳の分からぬまま鷹揚に受け容れている様まで、柳田があちこちで書き説いた日本の農村の移り変わりそのままである。町の若者が同意を求める仲間は、もはや島の外から来たロレンス夫妻なのだ。
無意識かも知れないが、そんな場面にこそロレンスの衝動が鋭敏に起こることが、この紀行文の意義をより深いものにしているのは間違いない。